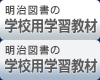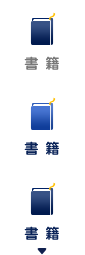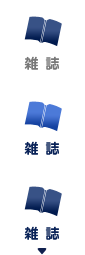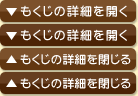- �܂�����
- ���́@�w�Z�m�̓]���Ƌ����w
- �P�@�w�Z�m�̓]���Ƃ͉���
- �u����̊�̓]���
- �u�w�ѕ��̓]���v�����߂�Љ�I�v���Ɗ���
- �w�Z�m�̓]���͉ʂ����ĉ\��
- �u�w�ѕ��̓]���v��}��ɂ�
- �Q�@21���I�����w�̉ۑ�
- ���}���`�V�Y�����烊�A���Y����
- �����~�g����
- �l�Ԋw����b�ɂ�������ߒ��̑����I����
- �����w�����̑Ώۂƕ��@�ɂ���
- 21���I������w���ʂ̉ۑ�
- ��T�́@�����̋Z�p�������w�̔��W
- �P�@�����R���̋����w
- �����̕��ՓI�Z�@
- �u�����R���v�������_�̔��W
- �������S��`�̋���
- �Q�@����̋Z�p�Ƃ��̑n���I���i
- �Z�p�Ƃ��Ă̋���w
- ����ɂ����鋳��Z�p�����̂����
- ����Z�p�̑n���I���i
- �R�@�w�K�w���i���Ɓj�̖ڎw�����͉̂���
- �w�K�w���Ƃ͉���
- �w�K�w���T�O�̌���
- �m���̋����ɂ���
- �u�m��Ώd�v�_�ւ̔ᔻ
- �m��̕s��
- �m���̋������ǂ��ʒu�Â��邩
- ���Ƃ̖ڎw�����͉̂���
- �w�K�w���Ɛ����w���Ƃ̗Z��
- ���Ƃ̖ڎw������
- �S�@���Ɖߒ��̖@����
- �����|�w�K�ߒ��̗��j�I�ϑJ
- �q�ǂ��̔F�������Ƒ�l�̔F������
- ���Ɖߒ��̌�����
- ���Ɖߒ��Ɋ܂܂�閵��
- ���ƓW�J�̌�����
- ���Ɖߒ��̊�{�I����
- �w���W�c���̈ӌ��Η�
- �T�@���Ƃ̋Z�p
- ���Ƃ̑S�̑�
- ���Ƃ̋Z�p�I�\��
- ���ތ���
- ���ނ̑I���Ɖ���
- ���Ƃ̐v
- ���Ƃ̓W�J
- �q�ǂ�����w�Ԏ��Ƃ̋Z�p
- �U�@�����̕��@
- �������@�̕���
- ���Ƃ̌`�Ԃƕ��@
- �����������Ƃ̕��@�\�\�u�̂ڂ肨��v�̎v�l�^��
- ��U�́@������e�\���_
- �P�@����ɂ����鋻���̌���
- �q�ǂ��̋�������o�����鋳��
- �{�\�_�Ƃ̌���
- ��ϓI�ϔO�_�Ƃ̌���
- �����Ɠw�͂̓��ꉻ
- �u�����̒��S�v�̋\�Ԑ�
- ����ɂ����鋻���Ɠw��
- �\���I���ӂƎI����
- �w�K�͘J���ł���
- �����͊����̂Ȃ��Ō`�������
- ���ړI�����ƊԐړI����
- �����̕���
- �W�c�̉e��
- �F���I�����̔��B
- �Q�@���Ȃ̌n�����̌���
- �n���w�K�͋l�ߍ��݂�
- �L���Ǝv�l�̔��B�Ƌ���
- �m���Ǝ��R
- �����I�T�O�̓���
- �ӎ����̖@��
- �����I�T�O�̔�̌n��
- �T�O�̑̌n��
- �Ȋw�I�T�O�̌`��
- �Ȋw�I�T�O�Ɛ����I�T�O�Ƃ̑��݊W
- �������S��`�̔��B��
- �A����`�̔��B��
- �b�����ƂƏ������Ƃ̔��B
- ���B�Ȑ��Ƌ���Ȑ�
- ���B�̍ŋߐڗ̈�
- �R�@�����ɂ������̐��̌���
- ��̐��ƒ��ϐ�
- �q�ǂ��͒��ۓI�Ɏv�l����
- �[�T�O�Ɛ^�̊T�O�̌`��
- ���ϐ��̌����̌�����
- ���ۓI�Ȃ��̂Ƃ͉���
- ���ۂ����̂ւ̏㏸
- �S�@�V�������ȓ��e�Ґ��̊�{����
- ���ȉے��u���㉻�v�̊�{����
- �u���������v�ƃ_���B�h�t���_�Ƃ̔�r
- �ʂ̎w���̌n�̑���
- �u���㉻�v����̋��P
- ����ے��S�̂̍\���Ƃ̊W
- �T�@�������Ă鋳��
- �����̉\��
- �V���������̌������鐶���Ƌ���
- ���s�����ꂸ�C���s����w�Ԏq�ǂ�����
- �����̂���[����������������o��
- ���R�Ƃ̏o��ƁC���̂�����J���̌�
- �|�p�͊���̊w�Z�ł���
- ��V�́@�w�ѕ��w�K�̗��_
- �P�@�w�ѕ��w�K�̌���
- ���^�w�K�Ƃ�
- �w�ѕ��w�K�_�̋O��
- �w�ѕ��w�K�̏���
- �u�w�K�̎d�����w�ԁv
- ���ꂩ��̊w�ѕ��w�K�̂����
- �u�w�ѕ����w�ԁv���ƂÂ���
- �u�₤���Ɓv���w�Ԏ��Ƃ̎��H��
- �w�ѕ��̓]����}����Ƃ̐�������
- �Q�@�����I�w�K�̗��_
- �u�����I�Ȋw�K�̎��ԁv�V�݂̂˂炢
- �����w�K�Ƃ͉���
- �����w�K�Ƌ��Ȋw�K�Ƃ͂ǂ��Ⴄ�̂�
- �����I�w�K���ǂ��n�邩
- �R�@�w�K�̌ʉ��ƌ��d���̌���
- �ʓI�ڋ߂̏d�v��
- �u���d���̌����v�Ƃ͉���
- ���d���̋��炪�{���ڎw������
- �w�K�̌ʉ��ƏW�c�w�K�̏��`��
- ���{�ƃA�����J�̌ʉ�����̔�r
- ����^�ɑ�ɂ��L���w�ѕ��̋���
- �S�@�u��b�E��{�v�̊m���Ȓ蒅��}��ɂ�
- �q�ǂ��̊w�ѕ��Ɗw�͂̌���
- �u����̊�̓]���v�͉ʂ����ĉ\��
- ���ȏ��͔��������悢�̂�
- �u��b�E��{�̊m���Ȓ蒅�v�͉\��
- �u��b�E��{�v���I�̂����
- ���ȓ��e���I�̊�{����
- �u��b�E��{�v�̊w�ѕ�
- �u����v����̊�b�E��{
- �u��b�E��{�v�̊m���ȏK����}��w�ѕ�
- ���Ƃ���
�܂�����
�@�����w�́C�w�Z�̎��Ƃ������ΏۂƂ��C���̗��_����}��w��ł���B����w�̂Ȃ��ŋ�����H�Ƃ����Ƃ����ڂɌ��т����w��ł���C�{���C���̒��S�Ɉʒu���ׂ��w��Ƃ����邪�C�킪���ł͂ǂ��炩�Ƃ����}�C�i�[�i�����I�j�ȑ��݂ł���B
�@���ۂɑ�w�ōu�`���ꂽ��C��������Ă��鋳��w�����Ă݂�ƁC�ӊO�ɋ�����H�Ƃ̂Ȃ���̔�������w���������Ƃɋ����B����́C������w�̋���w���ɂ͂���C����w�ɂ͂��߂Đڂ����Ƃ����ɕ��������z�ł���C�^��ł������B���́C���N�̍�����C�w�Z�̋��t�ɂȂ邱�Ƃ��Ă����̂ŁC����w�Ƃ������t�̐������Ƃ�����̕��@��Z�p���w�Ԃ��Ƃ��ł�����̂Ɣ��R�ƂȂ���v���Ă����B�������C��w�ŋ���w���w�Ԃ������ɂ��̊��҂��[������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B
�@��w�Ŋw���猴���Ƃ�����j�Ȃǂ����ɂƂ��Ė��Ӗ��������Ƃ����̂ł͂Ȃ��B���͂����̊w�K��ʂ��ē��{�≢�Ă̋���̗��j�E���x�E�v�z�Ȃǂ�������̒m���邱�Ƃ��ł��C�����傫���L���邱�Ƃ��ł����B������Љ�ۂƂ��ĂƂ炦�C������o�ςȂǑ��̎Љ�I�����ۂƂ̊֘A�̂Ȃ��ŁC�Љ�̑S�̍\���̂Ȃ��Ɉʒu�Â��āC���̖�����i�𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����������C���͑�w�Ŋw�Ԃ��Ƃ��ł����B
�@�������ċ���Ƃ������̂��L���Љ�I����̂Ȃ��łƂ炦�邱�ƂɐV�N�Ȗ��͂������Ȃ�����C���̍ŏ��̋^��͏����邱�Ƃ͂Ȃ������B����w�����ӂ̏��Ȋw�ƊW�������C�����̕��@�𗘗p���ċ��猻�ۂ͂�����C���߂��邱�Ƃɂ͈Ӌ`������Ƃ��Ă��C������H��ΏۂƂ���w��Ƃ��Ă͂Ȃ��̐S�̂Ƃ���ő���Ȃ����̂�����̂ł͂Ȃ����B�����C�����ԕ����͂��߂Ƃ��Ė��Ԃ̋��猤���^���ɊS���������̂́C���������^�₩��ł���C���̂Ȃ��Ō��o�����̂����Ƃڂ̌����ΏۂƂ���w�⁁�����w�ł������B
�@����w�̗��j��U��Ԃ��Ă݂�Ε����邱�Ƃ����C����w���Ɨ��̊w��Ƃ��čŏ��ɐ�������Ƃ��ɂ́C�����w�����̒��S�������߂Ă����B�����w�����̂��ׂĂł������Ƃ���������B17���I�̃R���j�E�X����19���I�̃w���o���g�w�h�܂ł́C����w�҂͂قƂ�ǂ��˂ɋ����w�҂ł������B�����́C���t�̋������������܂��܂̌`�ŗ��_�����邱�Ƃɓw�߂Ă����B
�@����w�����̌㕪�����āC����N�w�E����j�w�ȂǁC����w�̂��܂��܂̐�啪��W�����Ă��������Ƃ́C�����̐i�W�̂����œ��R�̐���s���ł������Ƃ����悤�B�������C���̊Ԃɂ��܂��܂̗��R���狳�猤���̎��H����̗V���Ƃ����X�������������Ƃ����������Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@���̗V���́C�������{�́u�w��Ƌ���Ƃ͕ʁv�Ƃ�����Ύ�`�I���琭��̂��ƂŒ������������猤���̎��R��D���Ă����킪���̋���w�ɂ����ĂƂ�킯�X���܂łɊg�債���B������e�����苳�ȏ��Ȃǂɂ���ēV����ɗ^�����C�������ꂽ��O�̊w�Z�ł́C���t�⋳�猤���҂����R�ɑn���I�Ȍ������s�����Ƃ͂ł��Ȃ������B���̂��߂ɋ���̕��@�E�Z�p�ɂ͌`����`���͂т���C����w�̌����̑����́C�����I��肩��V�������ϔO�̐��E�ɓ������Ă��܂����B���̍��ƌ��͂ɂ�鋳����e�̉��I�����́C��㋳����v�̎���Ɉꎞ�ɘa���ꂽ���̂́C���̌�̋t�R�[�X�̂Ȃ��ŏu���Ԃɕ������C�����Ɏ���܂ŋ��猤���̎��R��W����d�v�ȗv���ł��葱���Ă���B
�@�������C���C�����̋�����錠����F�߂��V���@�̂��Ƃł܂���Ȃ�ɂ�����I�ȋ���̌��݂��i�ނȂ��ŁC���������̋���w�̌��ׂ��傫����������Ă������Ƃ������ł���B�Ȃɂ����C���猻��ł̋����w�����̔��W�͂߂��܂������̂�����B�����w�̌����҂́C�ʂɑ�w�̊w�҂Ƃ͂�����Ȃ��B���H�҂ł��鋳�t���C���Ǝ��H�Ɍ����I�ɗ������������苳���w�̌����҂ł��蓾��B�܂��C�����������H�҂ł���Ɠ����ɗD�ꂽ�����҂ł����鋳�t�́C�����ɑ�ʂɐ��܂����B���ɁC�Ȋw�Ƌ���Ƃ̌����ɗ͂����Č�����i�߂Ă������Ԃ̋��猤���^���̂Ȃ��ł́C�e���Ȃ̐��Ƃł��苳���w�̌����҂ł�����D�ꂽ���t�������y�o���Ă���B
�@�����{�ɂ����鋳���w�����̂��̂悤�Ȕ��W�ځE�ԐڂɎx���Ă������̂́C�����̋���ɑ��鋭�����҂Ɨv���ł������Ƃ����悤�B�u�킩����Ɓv�ɑ���e�����̊��҂ɂ͐؎��Ȃ��̂�����B���ׂĂ̎q�ǂ��ɕ������āC���������x�̍������w����Ƃ��Ȋw�����n��o�����Ƃ�ڎw���Č�����i�߂Ă������Ԃ̋��猤���^���́C�������������̗v���ɉ����悤�Ƃ�����̂ł������B
�@�����C��w�ɂ����鋳���w�������C��㔼���I���o��Ȃ��ł������ɋ���w�̕Ћ�������d�v�Ȓn�ʂ��߂�悤�ɂȂ��Ă����B���{�̋���w�S�̂����n���Ƃ��K�����������ł͂Ȃ��̂����C�������̑�w�ł͋����w�����t�{���̒����I�w��Ƃ��Đ����Ɉʒu�Â�����悤�ɂȂ��Ă����B
�@�ɂ�������炸�C���{�̋���w�E�ŋ����w���ˑR�Ƃ��ă}�C�i�[�ł��葱���邱�Ƃɂ͂������̗v��������B�w�Z�̋�����e�i����ے��j�̉��I���Ɠ����́C���R�ȑn���I������j�ނ��̂Ƃ��āC���̑��̗v���ɂ������悤�B
�@���̗v���Ƃ��ẮC�����w�������̂��̂̓��e�I�E���@�_�I���������B������H�ƒ������������w�̌����ł́C���猻��ł̊ώ@�E�Q���E�����C���H�ƂƂ̋��������������߂��C����Ȃ镶�������ł͂��܂���Ȃ��B����w�̊w�ʘ_���́C�啔�����ߋ��̎v�z�j�����Ƃ����j�����ŁC�����̋�����H��ΏۂƂ�����̂��قƂ�ǂȂ��̂́C���H�����̓����[�I�ɕ�����Ă���B�������l�Ԃ����g�̐l�Ԃ�ΏۂƂ��čs������̎��H�́C������Z�p�̂Ȃ��ł��u�����Ƃ��L�͂ŕ��G�ȁC�����Ƃ������̋Z�p�v�i�E�V���X�L�[�j�Ƃ�����قǂɋɂ߂ĕ��G�ő@�ׁE�����ȋZ�p�Ȃ̂ł���B
�@��O�̗v���Ƃ��ẮC���A�����J���玝�����܂ꂽ�o����`�Ǝ������S��`�̋���w������B�q�ǂ��̋����E�S����o����厖�ɂ��邻�̋���v�z���C�킪�����̋�����v�ɂ����Ĉ��̐i���I�E�ϋɓI�������ʂ������Ƃ͔ے�ł��Ȃ��B�����C���̃A�����J�u�i����`�v�̋���́C�A�����J�{���ɂ����Ă��w�͒ቺ�������u���m����`�v�Ƃ��Ė{����`�ҁiEssentialist�j��������̔ᔻ��₦�����тĂ��Ă���悤�ɁC�Ȋw�E�Z�p�Ȃǐl�ނ̕�����Y���Ⴂ����ɒ����Ɍp������Ƃ��������w�I�Ȏd�����y�����邫�炢������B�Ƃ��낪�C�킪���̋���w�ł͂ǂ��炩�Ƃ����������s�̐�[�������O�҂̋���v�z���p�����̂�����I�ɂ��Ă͂₳��Ă����̂ł���B
�@���̂悤�ȃA�����J����w��ӓ|�̌X���́C���݂����炩���炢�ł��Ă͂�����̂́C�킪������E�ɂ����ĂȂ��h�邬����̂�����B���̓_�́C�h�C�c�𒆐S�Ƃ������[���b�p�̋���w�Ƃ͑ΏƓI�Ǝv����B���̂��Ƃ͍ŋ߁C���{��ꂽ�h�C�c�̋����w�҃}�C���[�́w���H�w�Ƃ��Ă̎��ƕ��@�w�x�iDr�DHilbert Meyer�CUnterrichts Methoden�P�CTheorieband�C1987�C�k��H���[�C1998�j������Ƃ悭������B�����ɂ͌���̃h�C�c�����w�ɉe����^���Ă���w�҂̖��O�ƗL���l�̏ё�����������[���u�����w�}�b�v�v���`����Ă���̂����C�}���N�X�E�w�[�Q���E�J���g�E�w���o���g���̏ё���͓��R�Ƃ��āC�s�A�W�F�E���B�S�c�L�[�E�_���B�h�t�E�X�L�i�[���̖��܂ł������Ă���̂Ƀf���[�C�̖��͌����Ȃ��B�{�����ł��C�f���[�C���v���W�F�N�g�E���\�b�h�Ƃ̊W�ł����ȒP�ɂӂ����ɂ����Ȃ��̂ͤ���������Ó����������悤�Ɏ��ɂ͎v����̂����C���ꂪ�h�C�c�����w�̌����Ȃ̂ł���B
�@�Ƃ���Ŏ��̋����w�����́C�f���[�C����w�Ƃ̊i������n�܂����Ƃ����Ă悢�B�����C�w�Z�̋��猻��ł̓A�����J����w�ւ̔ᔻ���ٓ������������̂́C�w�K�w���v�̂̍쐬�Ɋւ�鋳��w�҂͂��Ƃ���w�̍u�d�ł̓f���[�C�͂Ȃ����̌��Ђ��ӂ邤���݂ł������B�����C�f���[�C�ᔻ�̋��菊�Ƃ����̂́C��ɂ́C�����ԕ��Ȃǖ��Ԃ̋��猤���^���ł��������C���܈�ɂ́C���܂���ɂ����E�V���X�L�[�Ƃ����B�S�c�L�[�Ȃǃ��V�A�̋���w�E�S���w�����ł������B�f���[�C�����_�̔ᔻ���x�[�X�ɂ����{����U�͂P�߂̓��e�́C���̏C�m�_���ɂ�����E�V���X�L�[��������ɂ������̂ł���B�E�V���X�L�[�́C���������ȊO�ɂ͂��܂�m���Ă��Ȃ����݂����C�R���j�E�X�E�w���o���g�E�f���[�C�ȂǂƂ��䌨������̑�ȋ���w�҂��Ǝ��͕]�����Ă���B���B�S�c�L�[����{�ɏЉ���̂����͎����ŏ������C�ނ̑씲�ȐS���w���́C���̌�A�����J�o�R�ł��m����悤�ɂȂ�C���܂⋳��S���w�̐��E�ł��̖���m��ʐl�͂��Ȃ��قǂɂȂ����B
�@�������C���̌����̖���͂������ɓ��{�̋��猻�����̂��̂̂Ȃ��ɁC�Ƃ�킯�w�Z����ł̎��ƌ����ɂ̂߂肱�ނ悤�ɂȂ��Ă������B����͏��S�ɋA�邱�Ƃł������Ƃ����Ă��悢�B���t���u����҂̊w�ԋ���w���C���t�̎d���̒����ƂȂ���Ǝ��H�Ƃ͉I���̂��̂ł����Ă����͂��͂Ȃ��B
�@�����w�́C���ƂƂ������t�̋�̓I���H����ɂ��āC����Ƃ͉����C���ƂƂ͉����C���Ƃ̋Z�p�Ƃ͉����𖾂炩�ɂ��悤�Ƃ�����̂ł���B���Ƃ̂Ȃ��ł��肾������̓I��������ɂ��āC���̎����̂Ȃ����猴���I�Ȃ��́C�@���I�Ȃ��̂������o�����Ƃ���w��ł���B�������C���{�̋��t�̎��Ǝ��H����ɂ��C���{�̋��猻���ɍ����������w�������C�͂����Ă���܂łɂǂꂾ�����݂���̂��B
�@���́C���ԋ���^���ɎQ�����鋳�t�����C�n����������Z�p�����x�e�����̋��t�������C���ƌ����ł͂܂��������n�Ŏ�y�̎��ɂ��낢��Ƌ����C���������Ȃ���C���̂悤�ȋ����w�̌��݂Ƒn���ɑ傫�Ȋ��҂��Ă��邱�Ƃ�m���ėE�C�Â���ꂽ�B
�@�������ċɂ������Ă������̋����w������40�N�ȏ�ɂ��Ȃ�̂����C�ڎw���R�̂��������͉��[���C���܂��ɂ͂邩���̎�O�ł������Ă��銴��ۂ߂Ȃ��B�Ƃ����������̊ԂɎ������\���������w�W�̎�Ȓ����E�_���͊����Ɍf���Ă������B
�@���I���̓��{����E�́C���ς�炸���������̉ߔM�ƒ�N��C�A���Ȃ����߁C�N�X����������s�o�Z�C����ɂ͎q�ǂ��́u�V�����r��v�ɂ��w������Ȃǐ[���Ȗ��o������Ȃ��C�����E����͋����{�@�̉����Ă������o���ꂽ��C���m�������U�E�R�E�R�̊w�Z�̌n�ɂ��������̍\�����v�������������ŁC����܂ł̊w�Z����́u��̓]���v��}��Ƃ����悤�ȑ�K�͂ȋ�����v�Ă������Ƒł��o���ꂽ�肵�Ė��\�L�̍�����[�߂��܂܁C�V�������I���}���邱�ƂɂȂ����B
�@�w�Z�̋��猻��ł��̍������������t���T�낤�Ƃ���Ƃ��C��������Ȃ̂́C�q�ǂ������ɐ^�Ɋ���y�����C�悭�킩����Ƃ�n��o�����Ƃł���C�w�Z�����ɂ����������悤�Ȑ��k�����ł��w�K�ɂӂ����сu���C�v���N�����C���M�����߂��悤�Ȋy�������Ƃ�n��o�����Ƃł͂Ȃ����낤���B�����āC�����w�́C�{�����̂悤�Ȏ��ƂÂ���̎w�j�ƂȂ�ׂ��w��ł���Ǝ��͍l����B���܂��܂̍���Ȗ����������{�̊w�Z�̌���ł��̂悤�ȓ������Ƃ͌����Đ��Ղ������Ƃł͂Ȃ��B�������C���̓��͐V�������I�ɓ���������Ƃ����āC���Ƃ���ɐV�������̂�ǂ����߂邱�Ƃő���̂ł͂Ȃ����낤�B���s��ǂ��C�ނ�݂ɑ傫���h�ꓮ���̂̓A�����J�ɂ��œ��{�̋���E�̈������K���Ƃ�����B
�@���ƌ����ɂ����Ă��C�V�����w�����A�����J�Ȃǂ��������邱�ƂɔM���グ������i���̂悤�Ȍ��������Ӗ����Ƃ͌����Ă���Ȃ����j�C�܂��͋ߑ㋳���w�̖��炩�ɂ��Ă�������Z�p�̌�����@���Ɋw�ԂƂƂ��ɁC���{�̋��t�������グ�Ă������ƋZ�p�̋M�d�Ȉ�Y�ɂ�������w�Ԃ��Ƃ̕�����قǑ�ł��낤�B
�@�{�����C21���I�̊w�Z�Ǝ��Ƃ̂���ׂ��p���ǂꂾ����̓I�Ɏ����������C�܂������S���ƂȂ����C�����g�́C�����R�̂��������ւƑ������ɖڂ����Ȃ���C�V���ȒT���Ɍ����C�Â��Ƀt�@�C�g��R�₵�Ă���Ƃ���ł���B�ǎ҂̊��݂̂Ȃ��ᔻ�C���z��������������C�K���ł���B
�@�@2001�N�P���@�@�@�^�ēc�@�`��
-
 �����}��
�����}��