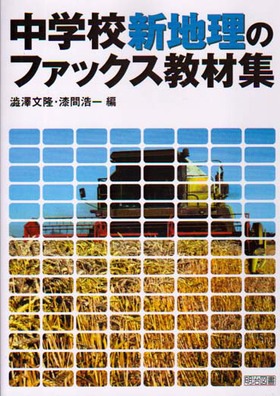- まえがき
- 1章 世界と日本の地域構成
- 1 私の国の裏側はどこ?―地球儀を使って調べてみよう―
- 2 国際電話にチャレンジ
- 3 赤道や経線を歩いてみたら
- 4 □と○と△で世界地図にチャレンジ
- 5 地名っておもしろい!似たものごとにまとめてみると
- 6 折れ曲がった日付変更線
- 7 不思議な大陸 南極大陸,不思議な海洋 北極海
- 8 いろいろな方向から日本を眺めてみると
- 9 わたしたちの北方領土
- 10 日本って大きい国,それとも小さい国?
- 11 日本って,南北に細長いの?
- 12 □と○と△で日本地図にチャレンジ
- 13 あなたはこんな地名を知っていますか?
- 14 さあ,日本をいろいろに分けてみよう
- 2章 地域規模に応じた調査
- 1 高いところから眺めてみよう
- 2 フィールドワークのコツを学ぼう
- 3 新しい地図記号を作ってみよう
- 4 これが私の分布図
- 5 縮尺を変えて学校の周りの地図を作ってみると
- 6 遠く離れた都道府県からデータをもらうには
- 7 「県勢」を解体してみたら
- 8 自分の都道府県をくもの巣グラフに描いてみよう
- 9 これが私の都道府県の上位10!
- 10 自分の都道府県を地域区分をしてみたら
- 11 これが私の都道府県のポスター!
- 12 世界の国の調べ方を伝授します
- 13 アメリカ合衆国ってどんな国?
- 3章 世界と比べて見た日本
- §1 自然環境から見た日本の地域的特色
- 1 世界的視野から見た日本の山脈・河川と平野
- 2 5つの気候帯からなる世界の気候
- 3 世界と日本の各地域の気温と降水量をグラフに表そう
- §2 人口から見た日本の地域的特色
- 1 世界人口と世界各州の人口の変化
- 2 千葉県と鳥取県を人口構成から比較してみると
- §3 資源や産業から見た日本の特色
- 1 農業のさかんな国・工業のさかんな国
- 2 日本の工業地域の変化
- 3 貿易品目から見た日本の特色
- §4 生活・文化から見た日本の地域的特色
- 1 住居から見た日本の地域的特色
- 2 日本の風土,日本人の味覚に合わせた食べ物
- §5 地域間の結びつきから見た日本の地域的特色
- 1 航空路線図から見た世界との結びつき
- 2 新幹線・高速道路から見た日本の地域的特色
- §6 様々な特色を関連付けて見た日本
- 1 日本PR作戦
- 2 一言で表す日本の特色
まえがき
“生きる力”をキーワードにした新教育課程がいよいよ実施段階になりました。学校教育は,子どもの成長を扶ける営みであり,長期的に,広い視野から検討する必要があります。入試を無視することはできませんが,一方で入試のみに通用するような打算的で功利主義的な教育であってはなりません。子どもたちが生きる近未来をみつめ,学ぶ豊かさを味わいつつ大人になって開花するような教育活動を展開する必要があるのです。
日本社会と同様に,中学校の社会科教育も改革の時代を迎えています。変化の時代は生涯学習の時代であり,学校教育は生涯にわたって学び続けるために必要な能力や態度の基礎を培うことが要請されています。変化の時代,科学が急速に進歩する時代は,知識が爆発的に増大する時代であり,そうした中で,古い知識を温存し,新しい知識を付加していくと,学習内容が膨大に膨れ上がり,パンクしてしまいます。変化の激しい社会においては,覚える学び方ではなく,変化する社会に関心を持ち続け,自ら社会認識を深めていく必要があります。そのためには,社会に関心を持ったり社会認識を深めたりするための座標軸になる知識を身に付けるとともに,いわゆる学び方を学ぶ必要があります。これからの社会科教育は,座標軸になる知識と学び方の両立を図った学習指導を展開する必要があるのです。
ところで,今,学校で社会科を担当している先生方は,自分自身の中学時代,高校時代に多かれ少なかれ知識詰め込みの社会科教育を受けています。そして,中学校教師になってからも,受験対策の社会科教育を展開してきています。そのため,知識詰め込みの社会科教育にどっぷり浸かり,教師主導型の講義式授業に慣れ親しんでいます。そうした先生方にとっては,生徒の主体的な学習を促したり,学び方を学ぶ学習指導を展開することは並大抵のことではありません。研修に努め,不得手さを克服し,意識転換を図る必要があります。それを,様々な仕事を抱え,慌ただしく多忙な日々を過ごしている中で実現するのは容易なことではありません。しかし,何とかしなくては生徒が犠牲になってしまいます。
せめてゼロからのスタートではなく,主体的な学習や学び方を学ぶ学習に結び付く教材が例示されるなど,何らかのきっかけをつくってくれれば,それを手掛かりに創意工夫するのだが…。本書はそうした要望を正面から受け止め,手掛かりを提供しようとするものです。本書に収められているファックス資料を実際に使い,生徒の反応などを通してワークシートの位置付けや開発,活用の仕方などを理解,把握し,作業的な学習,主体的な学習に慣れ親しんでいただければ幸いです。そして,本書を手掛かりに,先生方が自らワークシートの開発に乗り出していただければ幸いです。そうすれば,生きる力をはぐくむ社会科教育の実現の道が開けてくるものと思います。
編 者
-
 明治図書
明治図書