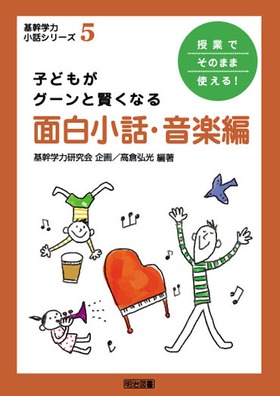- はじめに
- 本書の使い方
- Ⅰ 「音楽のはじまり」に関する小話
- 1 こうして地球に音楽が生まれた!<全学年>
- 2 日本に最初にやってきた西洋音楽は?<高学年>
- Ⅱ 「楽典」に関する小話
- 3 いつから? 五線におたまじゃくし?<中・高学年>
- 4 ドレミ…いつできたの?<中・高学年>
- 5 どうしてこんな形? ト音記号とヘ音記号<中・高学年>
- 6 音の階段 いろいろ<中・高学年>
- 7 おたまじゃくしだけじゃないよ!<高学年>
- 8 全部も半分もある…これって何?<中・高学年>
- 9 2拍子,3拍子…どこまであるのかな?<高学年>
- Ⅲ 「音楽のしくみ」に関する小話
- 10 まねっこ音楽~山びこみたい~<低学年>
- 11 音楽も会話しているの?<3学年以上>
- 12 まあるい音楽ってなあに?<2学年以上>
- 13 カノンちゃん,いろいろ<高学年以上>
- 14 行ってはもどる? A-B-Aの音楽(鑑賞学習を通して)<中学年以上>
- 15 これってただの音階でできているの?<中学年以上>
- 16 「ずらし」のテクニックでつくる音楽<中学年以上>
- 17 方向を逆にしてつくる音楽<高学年以上>
- 18 ポップスは,Aメロ,Bメロ,サビで…<中学年以上>
- 19 サイコロで作曲?<中・高学年>
- 20 楽譜のない音楽があるってホント?<高学年>
- 21 ピアノは何楽器?(ピアノの歴史とペダルの話)<全学年>
- Ⅳ 「楽器」に関する小話
- 22 楽器の王様,パイプオルガン<中・高学年>
- 23 カリヨン<中・高学年>
- 24 バイオリンが奏でるいい音の秘密<中学年以上>
- 25 ギターは6本,三線は3本<全学年>
- 26 管には金と木がある!(フルートは金管?)<中学年以上>
- 27 伸ばすとこんなに長いよ~私はホルン~<全学年>
- 28 大きくなる(長くなる)と低くなる?<中・高学年>
- 29 どうしてトライアングルは,三角形なの?<全学年>
- 30 竹でできている楽器,集まれー!<高学年>
- 31 石でできている楽器があるってホント?<全学年>
- Ⅴ 「目と耳で楽しむオーケストラ」に関する小話
- 32 指揮者のお仕事って大変なのね…<高学年>
- 33A 聴いてみよう,テレビで知ってるあの曲<中・高学年>
- 33B 聴いてみよう,テレビで知ってるあの曲<中・高学年>
- 34 玩具(おもちゃ)が活躍する曲がある!<全学年>
- Ⅵ 「音楽家」に関する小話
- 35 あの人も! この人も! 一族で音楽家?<高学年>
- 36 本当に天才だったの? モーツァルト<全学年>
- 37 超有名なベートーヴェン!<全学年>
- 38 本当にイケメンだった? ショパン<高学年>
- 39 動物がお好き? サン=サーンス<中・高学年>
- 40 J.シュトラウスとビゼーの不思議な偶然<高学年>
- 41 踊る旋律,チャイコフスキー<4学年以上>
- 42 絵から生まれた音楽~ムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」~<高学年>
- 43 「新世界」ってどこ? ~ドヴォルザークの「新世界より」~<高学年>
- 44 これも音楽? 4分半の沈黙~ジョン・ケージ『4分33秒』~<高学年>
- 45 この時代にカツラがあれば…山田耕筰<6学年>
- Ⅶ 「音や声」に関する小話
- 46 さまざまな声の音楽<中・高学年>
- 47 音にも色がある? 風鈴の「音色」から<高学年>
- 48 身体が楽器だ!<全学年>
- Ⅷ 「日本の音楽・世界の音楽」に関する小話
- 49 箏の形をよく見てみると…<高学年>
- 50 首振り3年,コロ8年~尺八~<高学年>
- 51 和太鼓の中をのぞいてみると…<高学年>
- 52 「打ち合わせ」ってどういう意味?<高学年>
- 53 「三拍子そろって」って本当はどういう意味?<全学年>
- 54 “合唱”が“世界遺産”?<高学年>
- 55 竹筒でリズムアンサンブル~トガトン~<中・高学年>
- 56 スーホの白い馬の楽器~馬頭琴~<全学年>
- 57 指揮者って本当に必要なの?(西洋と東洋の合奏の違い)<高学年>
- Ⅸ 「エンターテイメントと音楽」に関する小話
- 58 オペラってなあに?<高学年>
- 59 どこが違う? オペラとミュージカル<高学年>
- 60 ミュージカルって楽しいよ『サウンドオブミュージック』<中・高学年>
- Ⅹ やってみよう!
- 61 一つの音でオッケー(リコーダー)<3学年>
- 62 二つの音でオッケー(リコーダー)<3学年>
- 63 三つの音でオッケー(リコーダー)<3学年>
- 64 リコーダーCM特集<中学年>
- 65 100円ショップから生まれる管楽器!<全学年>
- 66 身近で楽しむ自然の音楽~草笛~<全学年>
- 67 歌ってあそぼう! あそんで歌おう!<低学年>
- 68 踊る! 鍵盤ハーモニカ!<低学年>
- ⅩⅠ アラカルト
- 69 学校のチャイムのメロディは日本人がつくったの?<全学年>
- 70 CDのしくみ<高学年>
- 71 星も音楽を奏でているってホント?<高学年>
- 72 子守歌はおまじない?<高学年>
はじめに
〈エピソード1〉
「学級崩壊は,音楽から始まる…」というショッキングな話を耳にしたことがあります.そんなことはあるはずがない,と声を大にしていいたいところですが,いい切れない自分もここにいます.
子どもたちに「学校の勉強で何が最も好きか.その次は何か.好きな順にその教科名を答えてください」と問うたことが何度かあります.すると「体育」や「図工」などに次いで音楽は必ずといっていいほど上位にランクされます.それなのになぜ学級崩壊が….本当におこるのでしょうか?
〈エピソード2〉
また,その一方でこんな話もあります.音楽の時間が好きな理由についてです.「楽しいから」「音楽が好きだから」…これは予想できる答えですね.しかし「息抜きができるから」という理由をあげる子も少なくないと聞きます.どう解釈したらいいのでしょう?
〈エピソード3〉
逆に,「音楽が嫌いだ」という子に話を聞いてみると,だいたい次のような答えが返ってきます.「いつも歌ってばかりだし,口のあけ方や声の出し方を厳しく教えられる」「いつもリコーダーばかりでつまらない」「家で聴く音楽は好きだけど,学校の授業は好きじゃない」と.音楽って楽しいものですよね,本当は….
〈エピソード4〉
「歌唱」「器楽」「創作」「鑑賞」をそれぞれどのくらいの時間を割いているか,という調査があったそうです.すると,予想通り「歌唱」や「器楽」にもっとも多くの時間が割かれていたそうです.しかし「鑑賞」は20%以下,「創作」についてはさらに少ない時間しかあてられていない.ひどい場合には「創作」はおこなっていないという学校も少なくないのだそうです.
これらの話を総合して,私は次のように考えました.
1.音楽の授業は,やはり「楽しく」なければならない.
2.技能偏重の授業だけでは,音楽を好きにはさせられない.それこそ,学級崩壊を招きかねない.
3.「歌唱」や「器楽」の授業だけで,音楽の力を身につけられるとは思えない.
↓
音楽指導のポイントがわからない,授業をどのように進めたらいいのか困っている先生もいるのではないか…
全国的にみて,音楽の授業は全学年とも学級担任がおこなうケースが多いようです.しかし,一般的にいって,すべての教師が音楽の専門的な知識や,知っていて得をするような雑学をもち合わせいるとはいえないでしょう.前記でもふれたように,音楽の授業をどのように進めたらいいのか困っている先生もきっとたくさんいるのではないでしょうか.
そこで,誕生したのが本書なのです.授業の中で子どもにそのまま話せるトピック(小話)集です.子どもが「ヘェ~~~!そうなんだ」と感心できる,そんな内容がぎっしり詰まっています.
たとえば,音楽家の話が載っています.『この時代にカツラがあれば…山田耕筰』のページをちょっと読んでみてください.これは完全な雑学です.直接音楽の中身につながる話ではないかもしれません.でも,この話を聞いた子どもは,おそらく山田耕筰という音楽家の名前を簡単には忘れないでしょう.
また,『玩具(おもちゃ)が活躍する曲がある!』のページを開いてみてください.「おもちゃのシンフォニー」という曲を楽しく鑑賞する方法が見出せることでしょう.もちろん楽しいだけではありません.その学習を通してどんな音楽の力をつけられるのかも明確に示されています.この話を聞いた子どもは,「どんな音が聞こえてくるかな?」と目をキラキラ輝かせて授業に参加するでしょう.
このように,音楽に関心をもたせたり,確かな力をつけられたりするのは,実はほんのちょっとしたきっかけだと思います.そのきっかけづくりに本書をぜひ参考にしてください.楽しい音楽の授業,その積み重ねが,生涯を通して音楽を愛好する子どもの育成に結びつくと確信しています.
本書は,全国各地で,音楽の授業を楽しく,そして実りあるものにしようと日々がんばっている仲間で執筆しました.本書をお読みになって「これなら私にもいい授業のアイデアがある!」とお思いになられる方もたくさんいらっしゃるでしょう.ぜひ仲間になってください.さらに先生たちのネットワークを広げ,みなさんでこの本を育てていただき,「あぁ,今日も音楽の授業が楽しかった~!」と感じる子どもを一人でも多く増やそうではありませんか.
最後に本書の作成にあたり企画を立ち上げてくださった基幹学力研究会,ならびに明治図書編集部の樋口雅子氏に心より感謝いたします.
筑波大学附属小学校 /髙倉 弘光
-
 明治図書
明治図書