- はじめに
- 第1章 問いづくりと探究の授業デザイン 5つのポイント
- Point1 子どもの実態・目標・材・教師の個性を考慮して
- Point2 探究の授業デザインの核「ゴールの設定」
- Point3 問いづくりについて
- Point4 その子らしい学びへ
- Point5 子どもの頭の中を見る
- 第2章 問いづくりと探究の授業デザイン 16のスキル
- 1 授業デザインをするにあたって 問いをもつにも経験が必要
- 2 授業デザイン 子どもの様子と学習内容→授業デザイン→個々の問い
- 3 授業デザイン 子どもの心に火がつくかは、単元のゴールの設定次第
- 4 問いづくり 子どもが問いを抱くには、教師の仕掛けが不可欠
- 5 問いづくり 問いの精選
- 6 パフォーマンス評価 子どもの姿を見取るために
- 7 パフォーマンス評価 ルーブリックを作成する
- 8 探究を支える手立て 子どもがよりよい学び方に気づく言葉かけをする
- 9 探究を支える手立て 社会科の本質に迫る言葉かけをする
- 10 探究を支える手立て 様々なツールを活用する
- 11 探究を支える手立て 目的に応じた板書
- 12 探究を支える手立て 振り返りの活用①
- 13 探究を支える手立て 振り返りの活用②
- 14 探究を支える手立て 対話するメンバーの構成
- 15 共有するための手立て つなげるように 見えるように
- 16 共有するための手立て 共有したものを個に返す
- 第3章 問いづくりと探究の授業デザイン 15の実例
- 【3年生】(店ではたらく人びとの仕事) スーパーマーケットにたくさんの人が買い物に来るのは
- 【3年生】(火事から人びとを守る) 子どもの様子から授業デザインを修正する
- 【4年生】(くらしをささえる水) ダム建設の背景
- 【4年生】(自然災害から命を守る) いつもモヤモヤして終わる授業
- 【4年生】(わたしたちのまちに伝わるもの) 国語×社会科で授業デザイン
- 【5年生】(さまざまな土地のくらし~高い土地・低い土地~) 選択単元を選択しない
- 【5年生】(さまざまな土地のくらし~あたたかい土地・寒い土地~) おすすめするなら?
- 【5年生】(自然災害から人々を守る) 子どもの問いを見通して
- 【6年生】(日本国憲法と政治のしくみ) あなたが裁判員に選ばれたら
- 【6年生】(わたしたちの願いと政治のはたらき) 区長に来年度の予算を提案しよう
- 【6年生】(大昔のくらしとくにの統一) 縄文時代と弥生時代のくらしは、どちらが幸せか?
- 【6年生】(武士による政治のはじまり) 目が覚めると武士だった…家来になるなら?
- 【6年生】(戦国の世の統一) 日常的に「楽しく」使う成果物を単元のゴールに
- 【6年生】(歴史・江戸の社会と文化・学問) あなたが気になる人物は?
- 【6年生】(日本とつながりの深い国々) あなたが紹介したい国は
- Column
- ・「個別最適な学び」と聞いて、モヤモヤ~
- ・「その子らしい学び」の実現に向けて
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
本書を手にとっていただき、誠にありがとうございます。佐野陽平と申します。
早速ですが、この本に関心をもたれたということは、次のような思いを抱かれているのではないでしょうか?
「問いを大切にしながら社会科の授業を進めていきたい」
「社会科で探究的な学びを進めていきたい」
まさに、本書のタイトルにある「問い」「探究」は、これからの授業デザインのキーワードとして注目されています。きっと皆さんは、これらのキーワードを授業実践に取り入れながら、深い学びの実現に向けて、日頃より努力されている方なのだと想像します。私も、日々、試行錯誤している一人です。
その中で、本書は、私が悩みながら取り組んできた実践をベースに、次のことが書かれています。
・教師は、問いづくりと探究の授業デザインをするために、何を考えるのか(第1章)
・どのように問いをつくるのか、教師はどのように仕掛け・支えるのか(第2章)
・子どもが探究していくには、教師がどのように仕掛け、支えるのか(第2章)
・子どもの姿が見える問いづくりと探究の授業デザイン15の実例(第3章)
実践と経験を重ねるにつれ、ただ「授業がうまくなりたい」という思いから、「その子らしく学び、その子に力がつく授業をしたい」と、めざす授業像を少しだけ具体的に言語化できるようになってきました。まだまだ私は未熟ですので、「いやいや…」と感じられる部分も多いと思います。しかし、本書の中には、子どもが問いからその子らしく学び始める姿や、その子らしく探究していく姿を感じてもらえる部分もあるかと思います。そして、お読みになられた方が、その方らしく「自分は、こうしてみよう」「ちょっと挑戦してみようか」「ここは大切だな」といったことを見つけていただければ幸いです。
2025年6月 /佐野 陽平














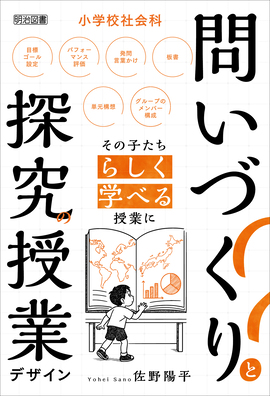
 PDF
PDF


読んでいるとまるで著者の方と社会科について話しているような気持ちになります。
肩肘張らない、でも本質に迫る
ICTも必要なら使う、アナログの方が有効ならそちらで
授業方法も使えるものは使うし、でもそれにこだわりはしない
飄々と良い授業をしている方の日常的な社会科が詰まった、現場教員にとって等身大(でも実はとても質の高い)の1冊です。