- まえがき
- Chapter 1 子どもが主語の理科授業に必要なこと
- 第1部 理科の本質に迫る
- 1 理科の面白さを追究する
- 2 領域固有の面白さを追究する
- 3 本物の学びを実現する
- 第2部 授業デザイン
- 1 単元をデザインする
- 2 観察,実験をデザインする
- 3 対話と探究の授業文化をつくる
- 第3部 未来の理科教育
- 1 デジタル×理科の学びを生み出す
- 2 複雑な問題を解決する
- 3 最先端のICTで未来社会に向かう
- Chapter 2 子どもが主語になる理科授業のしくみ30
- 理科の面白さを追究する
- 1 問題を見いだすしくみ
- 2 予想を発想するしくみ
- 3 実験を計画するしくみ
- 4 考察をするしくみ
- 領域固有の面白さを追究する
- 5 エネルギー領域の面白さに迫るしくみ
- 6 粒子領域の面白さに迫るしくみ
- 7 生命領域の面白さに迫るしくみ
- 8 地球領域の面白さに迫るしくみ
- 本物の学びを実現する
- 9 「学びの文脈」を大切にするしくみ
- 10 「失敗」から始まる科学のしくみ
- 11 自然観を醸成するしくみ
- 単元をデザインする
- 12 子どもの素朴概念を生かすしくみ
- 13 教科書の学びを広げるしくみ
- 14 地域や社会とつなぐしくみ
- 観察,実験をデザインする
- 15 実験キットにたどり着くまでのしくみ
- 16 生命の神秘さに迫るしくみ
- 17 夜間観察を充実させるしくみ
- 対話と探究の授業文化をつくる
- 18 聴くことで対話が深まるしくみ
- 19 学びに著者性をもたせるしくみ
- 20 相互参照で全員を巻き込むしくみ
- デジタルとアナログを行き来する
- 21 「見えない」を見える化するしくみ
- 22 試行錯誤が楽しくなる観察のしくみ
- 23 NHK for Schoolで学びを深めるしくみ
- 複雑な問題に向き合う
- 24 複数の切り口がある問題に向き合うしくみ
- 25 システム思考で世界を読み解くしくみ
- 26 防災を自分ごとにするしくみ
- 未来社会を感じる
- 27 空からの視点で学びを変えるしくみ
- 28 360度の視野で世界を捉えるしくみ
- 29 プログラミングでリアルを追究するしくみ
- 30 生成AIと共に考える力を育むしくみ
- あとがき
まえがき
みなさんは,理科の授業でこんな悩みに直面したことはありませんか?
「実験や観察は盛り上がるのに,予想や考察になると子どもたちの興味が続かない…」
「子どもたちが自分の考えを出し合い,学び合える授業にしたいけれど,どうすればいいのかわからない…」
「単元ごとにバラバラになりがちな学びを,もっと子どもたち自身の中でつながるようにしたい…」
もし一つでも思い当たることがあれば,この本はきっとあなたの授業づくりの助けになるはずです。これまでにも,理科授業のヒントや実践例をまとめた優れた書籍は数多く出版されています。どれも現場の教師の思いと工夫の結晶であり,私自身も大いに学び,支えられてきました。本書はそれらの蓄積に敬意を払いながら,少しだけ視点を変えて書いた1冊です。
私がこの本で提案したいのは,「子どもが主語になる理科授業」です。単に教師が説明したり子どもが実験を楽しんだりするだけではなく,子ども自身が自然事象に出会い,問題を見いだし,予想し,計画を立て,観察や実験を行い,結果を整理して考察し,結論を導くという学びのプロセスを中心に据えています。このプロセスこそが「理科ならではの学び」であり,深い学び(Authentic Learning)の出発点になると私は考えています。
私はこれまで8年間,附属小学校に勤務し,多くの公開授業の機会をいただきました。そのたびに「附属だからできるのでは?」という声を耳にしました。しかし,全国の多様な学校や先生方と授業づくりに取り組む中で確信したのは,附属校と公立校の間に本質的な違いはないということです。そして今年度,公立小学校に戻り,改めてそれを実感しています。どの学校でも,子どもたちは理科に夢中になり,学び合い,高め合う力を存分に発揮しています。子どもが主語になる授業づくりの本質は変わらないのです。
なお,本書の内容はすべて現場の実践に基づいています。空想や机上の理論ではありません。附属時代には4年生理科の担当経験がなかったため,4年生の事例紹介は少なめであることをご了承ください。
正直に言えば,私は決して「理科が得意な教師」ではありません。しかし,地学分野は大好きです。新月の夜には満天の星空を求めて車を走らせ,旅先では「今,天竜川通過」などと川の名前で現在地を伝えるほど河川にも魅力を感じています。本書に天文や河川の題材が多いのは,私自身がその面白さに魅せられているからです。「教師自身が単元や題材を面白がっていること」こそが子どもが主語になる授業づくりの第一歩だと私は思います。どうか読者の皆さんも,自分なりの「推し単元」をぜひ見つけてください。
本書は,私自身の試行錯誤と,全国の先生方の実践知を結びつけた「現場のための実践共有」です。この本を読み進めていくうちに,「ああ,こういう場面で子どもの思考をもう一歩深められるのか」「この単元のねらいをこんな視点からデザインできるのか」と,読者であるあなた自身の授業観・子ども観が豊かに揺さぶられる瞬間が訪れることを願っています。
2025年7月 /前田 昌志
-
 明治図書
明治図書- 実験観察が大好き!と言う子どもたち。目を輝かせる姿は見ているこちらも嬉しくなるが、それだけでいいのだろうか?そんな悩みに応えてくれたのが本書である。これからも理科授業のバイブルとして大切にしていきたい一冊になった。2025/9/2120代・小学校教員














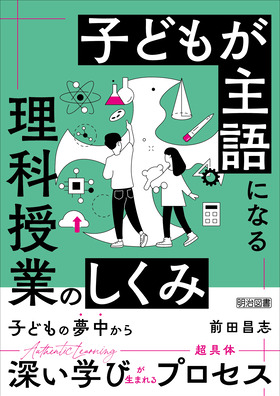
 PDF
PDF

