- はじめに
- 第1章 自主学習で自己調整できる子供を育てる
- 1 宿題・自主学習を自己選択・自己決定できる学習へ
- 2 自己調整学習力とは?
- 3 学習における自己調整力の重要性
- 4 自己選択による学びの促進
- 5 自己決定がもたらす変革
- 第2章 自主学習を始める前に押さえておきたいこと
- 1 自主学習で目指すものは?
- 2 自主学習が育む自分らしさ
- 3 信じる・見守る・支える
- 4 生活すべてが学びの場
- 第3章 自主学習で自己調整力を高めるアイデア
- 1 自主学習をスタートする前の語り
- 2 一斉自主学習勉強会
- 3 ノートに名前をつける
- 4 マイルールをつくる
- 5 目標を立てるスキルを身につける
- 6 成長を実感しやすい仕組みづくり
- 7 学習内容を選択する・決める
- 8 学び方を決める
- 9 ネタ帳作戦
- 10 自学チップ
- 11 自主学習交流会
- 12 悩みの雑談会
- 13 学級通信で価値づける
- 14 自主学習コーナーの設置
- 15 努力に対する語り
- 16 自学ザベスト
- 17 オリジナルキャラクターと学ぶ
- 18 自学事典
- 19 自主学習の記念写真
- 20 じっくり向き合えているときの語り
- 21 自主学習モンスター討伐作戦
- 22 「自学総選挙」開幕
- 23 過去の学びをもう一度
- 24 自分の学びでつくるクイズ大会
- 25 年間の自主学習ベストを決める
- 26 自立した学び手たちへの語り
- 第4章 自己調整力を高める振り返りとフィードバック
- 1 振り返りとフィードバックの重要性
- 2 努力メーターで努力値算出
- 3 種類別振り返りシートでさらなる成長を
- 4 会話でのフィードバック
- 5 文章でのフィードバック
- 6 保護者からのフィードバック
- 第5章 自主学習に困ったときのQ&A
- Q1 自主学習で決まった内容にしか取り組みません
- A 興味を引き出す対話や選択肢を用意して、成功体験を積ませましょう
- Q2 頑張っているけれど知識が定着しません
- A まずは、知識が定着しない要因を特定しましょう
- Q3 長い時間、内容を決められず悩んでいます
- A 選択肢を提示し、一緒に考えましょう
- Q4 時間がなくて、自主学習に取り組めません
- A 自主学習のハードルを下げて対応しましょう
- Q5 教師はどこまで介入すればいいのですか?
- A 直接教えるというより、伴走者として介入する気持ちが大切です
- Q6 苦手な学習はやろうとしない子がいます
- A 挑戦できる場の確保・スモールステップの目標設定・学習方法の工夫が大切です
- Q7 妥協して学習量が少なくなってしまいます
- A 押しつけずに、本人に気づかせる対応をしましょう
- Q8 学習に興味をもてない子への対応はどうしたらよいですか?
- A 興味の探求とごほうび作戦で学習のきっかけをつくりましょう
- おわりに
- 参考文献一覧
はじめに
私が自主学習に本格的に取り組み始めたのは、教師としてのキャリアをスタートして間もない頃でした。最初は、ただ出すだけという程度のもので、特別な意味をもって実践していたわけではありませんでした。
しかし、あるとき、教室で子供たちのノートを見ていると、心から真剣に取り組んでいる子がいる一方で、こなすことが目的となっている子もいるように感じました。
今の自主学習にどれだけ意味があるのだろう?
どうすれば学ぶ楽しさを見いだせるのだろう?
どうすればもっと意味のある自主学習になるのだろう?
それが私の問いのはじまりでした。そして、取り組み続けるうちに1つの答えにたどり着きました。
自主学習は、とりあえずやらせるものでも、こなすだけのものでもない。
自主学習は、人生を自らの手で切り開く力を育むもの。
子供たちは、日々の様々な出来事のなかで、迷い、悩みながらも、少しずつ自分のあり方を模索しています。そんななかで自主学習に取り組む時間は、「自分の興味や疑問に正直になれる時間」「自分自身と真剣に向き合う時間」として機能します。
10年以上、自主学習に向き合っていて思うのは、伸びていく子供たちには共通点があります。それは、「学ぶ楽しさを知り、自分自身と向き合い、調整しながら進んでいける力」をもっているということです。これこそが、自己調整力であり、今、教育において最も必要な資質だと考えています。
「今日は何を学ぼうかな?」
「今日はどうやって進めようかな?」
「明日はどうやって学んでみようかな?」
このような問いを自分で日々繰り返すなかで、子供たちは確かに変わっていきます。自分の学びを人任せにせず、「自分事」として捉えるようになります。
そこに至るまでは、時間も根気も技能も必要です。ときには、思うようにいかないこともあります。それでも、
子供たちを信じ続けること。
子供たちと本気で向き合い続けること。
その積み重ねが、子供たちのなかに学びの根っこを育てていきます。
本書では、このような考えをもとに、10年以上試行錯誤して取り組んだ内容を載せています。
本書のなかで紹介するのは、
・自主学習の本質とは
・子供たちのやる気を引き出すための工夫
・学級全体での取り組み方法
など、日々の実践や子供たちとともに向き合ってきた現場のリアルです。いわゆるテクニックや成功した方法にとどまらず、子供たちと過ごす日々での対話や、自分の失敗から学んだことを中心に、同じ教育者としての視点を共有したいと思って書きました。
また、本書を書いた目的は、単に自分の教育論を述べるためだけではありません。クラスで自主学習を始めたいと思っている人、子供たちに自主学習でもっと力をつけたいと願っている人のヒントになればと思っています。
子供たちが学びを通じて、自分を好きになれるように。
自分の可能性を信じ、人生を切り開いていけるように。
教師自身も、迷いながらも確かな軸をもって指導できるように。
そんな想いを胸にこの本を書き上げました。もし、みなさんの心に少しでも響くものがあったとしたら、これ以上の喜びはありません。
さあ、子供たちの未来を信じて、一緒に歩んでいきましょう。
/瀧口 直樹














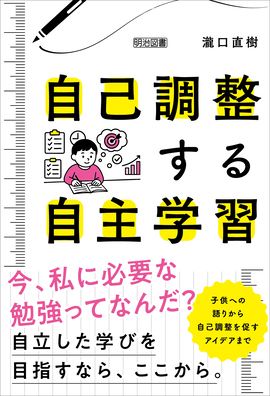
 PDF
PDF


子どもたちの「学びたい!」を喚起し、生涯学習の基盤を築く本書は、これからの教育に関わるすべての人にぜひ呼んでいただきたい一冊です!