- �͂��߂�
- �T�@���Ȃ̋��猴��
- �P�@����
- �Q�@���ȋ��猤��
- �R�@�Ȋw��
- �S�@���R��
- �T�@�Ȋw�̐����iNature of Science�j
- �U�@�Ȋw�̕��@
- �V�@�Ȋw�I���_
- �W�@�w�⒆�S�J���L������
- �X�@�l�Ԓ��S�J���L������
- 10�@������
- 11�@���ȋ���U���@
- 12�@���ȋ���̌��㉻
- 13�@STEM/STEAM����
- 14�@Socio-scientific Issues�iSSI�j
- 15�@�T�C�G���X�E�R�~���j�P�[�V����
- 16�@������
- 17�@���R�̌�����
- 18�@���n�ƕ��n
- 19�@�W�F���_�[
- 20�@�_�C�o�[�V�e�B�E�C���N���[�W�����iD & I�j
- �U�@���Ȃ̖ڕW�Ɠ��e
- 21�@�Ȋw�I���e���V�[
- 22�@�R���s�e���V�[
- 23�@�Ȋw�I�m��
- 24�@�Ȋw�I�v�l
- 25�@�Ȋw�A�C�f���e�B�e�B
- 26�@���w�Z�w�K�w���v�̂̕ϑJ
- 27�@���w�Z�w�K�w���v�̂̕ϑJ
- 28�@�����w�Z�w�K�w���v�̂̕ϑJ
- 29�@���Ȃ̓��e�\��
- 30�@��������
- 31�@�G�l���M�[�T�O
- 32�@���w����
- 33�@���w�̊�{�T�O
- 34�@��������
- 35�@�i���T�O
- 36�@�n�w����
- 37�@�n���V�X�e���̊T�O
- 38�@������
- 39�@�h�Ћ���
- 40�@���S����ƈ��S�Ǘ�
- �V�@���Ȃ̋�����@
- 41�@�������^�������w�K
- 42�@�Ȋw�I�T���^�T���w�K
- 43�@�v���Z�X�E�X�L���Y
- 44�@���̌�������
- 45�@�����ݒ�
- 46�@�ώ@�E����
- 47�@��������
- 48�@���،v��
- 49�@���́E����
- 50�@�O���t�̊��p
- 51�@�A�[�M�������g
- 52�@���̂Â���
- 53�@����E�͔|
- 54�@���f���x�[�X�w�K
- 55�@�A�i���W�[
- 56�@�����w�K
- 57�@�^���̊w�K�i�I�[�Z���e�B�b�N�E���[�j���O�j
- 58�@�Ȋw�j��p�����w�K
- 59�@�C���t�H�[�}������
- 60�@�˔\����
- 61�@ICT�̊��p
- 62�@���t���N�V����
- �W�@���Ȃ̊w�K�ƔF�m
- 63�@���R�F��
- 64�@�f�p�T�O�E��T�O
- 65�@�T�O�ϗe
- 66�@�\����`
- 67�@���ꂩ��
- 68�@�]��
- 69�@���[�j���O�E�v���O���b�V�����Y
- 70�@�F�m���B
- 71�@�c�����̉Ȋw����
- 72�@��ԔF�m
- 73�@�n����
- 74�@�F���I�F�m
- 75�@�Ȋw�j���[�X�̐M����
- 76�@���^�F�m
- 77�@�ᔻ�I�v�l
- 78�@�m�I������
- 79�@���@��
- 80�@�L�p���̔F��
- 81�@���Ȓ����w�K
- �X�@���Ȃ̊w�K�]��
- 82�@�]���̎��
- 83�@�w�K�̕]��
- 84�@�w�K�̂��߂̕]��
- 85�@�w�K�Ƃ��Ă̕]��
- 86�@�`��@
- 87�@�R���Z�v�g�}�b�v
- 88�@�t�B�[�h�o�b�N
- 89�@�A�Z�X�����g�E���e���V�[
- 90�@�w�͑���
- 91�@�R���s���[�^�[�g�p�^�e�X�g�iCBT�j
- �Y�@���Ȃ̋��t����
- 92�@���t�̐��I����
- 93�@Pedagogical Content Knowledge�iPCK�j
- 94�@���U�ɂ킽�鋳�t�Ƃ��Ă̐��I����
- 95�@�������C
- 96�@�w�K�w����
- 97�@���ƌ���
- 98�@���ތ���
- 99�@�n�拳��
- 100�@�A�N�V�����E���T�[�`
- 101�@���_�Ǝ��H
- �Z�@���O���̉Ȋw����ƍ��۔�r
- 102�@�A�����J�̉Ȋw����
- 103�@�C�M���X�̉Ȋw����
- 104�@�h�C�c�̉Ȋw����
- 105�@�t�����X�̉Ȋw����
- 106�@�J�i�_�̉Ȋw����
- 107�@�����̉Ȋw����
- 108�@��p�̉Ȋw����
- 109�@�V���K�|�[���̉Ȋw����
- 110�@���ۋ��狦��
- 111�@PISA
- 112�@TIMSS
- 113�@TALIS
- 114�@ROSES
- ���������F���ȋ���Ɋ֘A����w���G��
- ����
- ���M�҈ꗗ
�͂��߂�
���ȏd�v�p�ꎖ�T�ҏW�̈Ӑ}
�@�������́C���w�Z�R�N���ɂȂ�ƁC������O�̂悤�Ɋw�Z�ŗ��Ȃ��w��ł��Ă��܂��B���w�Z�⍂�Z�ł��D�������Ɋւ�炸�C�S�Ă̐��k�����Ȃ��w�Ԃ��ƂɂȂ��Ă��܂��B�������Ȃ���C���������C�ǎ҂̊F����́C�Ȃ��w�Z�ŗ��Ȃ������K�v������̂��ɂ��āC���₵����搶�ɐq�˂��肵�����Ƃ͂������ł��傤���B�܂��C�q���̍��ɁC���Ȃ������Ă����搶���C�ǂ̂悤�ɓw�͂��Ȃ��玙�����k�̂��߂ɋ��ތ��������s���Ă��Ă��邩���C���������C�z���������Ƃ͂������ł��傤���B
�@���ȏd�v�p�ꎖ�T�i�ȉ��C�{���T�j�̓ǎ҂́C���ȋ��猤���ҁC�����C��w�@���E��w���������Ǝv���܂����C��w�ŗ��ȋ���@���̋��E�Ȗڂ���Ȗڂ𗚏C���ď��߂āC���ȂƂ͉����C�Ȃ����Ȃ�������̂��C�ǂ̂悤�ɂ��Ď������k�̗���x��c������̂��C�������k�̊w�т��x�����鋳�ނƂ͉��������l���n�߂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���ȋ���Ɍg���C���邢�͂��ꂩ��g���l�����́C���ȋ���̗��_�Ǝ��H�̊W�C����܂ł̗��ȋ���̌����Ƃ��ꂩ��̗��ȋ���̌����̋��ʓ_�Ƒ���_�C�w�K�w���v�̂Ƌ��ȏ��̊W�◝�Ȏ��ł̎��H�݂̍���C�q���̐������x������w�ё����鋳�t�����C�ߋ���U��Ԃ�Ȃ���Ȏ@���C�����Ɍ����Ă̕��������l���o���Ă������ƂɂȂ�܂��B
�@�{���T�́C���ȋ���̍����I�Ȗ��C���ȋ��猤���̌���̔c���Ɛ����̌���C���ȋ��猤���̗��_�I�ȃt���[�����[�N�C���H�ɂ�����ۑ�Ɖ����̂��߂̌������@������̓I���킩��₷��������邱�ƂŁC���ȋ��猤���̐i���◝�ȋ���̎��H�̐V�����W�J�̂��߂̈ꏕ�ɂȂ邱�Ƃ���}���ĕҏW�����Ă���܂��B
���ȏd�v�p�ꎖ�T�̓��F�ƈʒu�Â�
�@����܂ł킪���ł́C���ȋ���̗p�ꎖ�T�i���T�j�͂�������������Ă��܂����B���̂悤�ȏ̒��ŁC�{���T�ɐ旧�������}�����玟�̏��Ђ���������Ă��܂����B�����́C傒J�Ďi�E�ؑ��m�וҒ��i1981�j�w���ȏd�v�p��300�̊�b�m���x�i���ȋ���̊�b�p��V���[�Y�j�C���̉����łɂ����镐���d�a�E�H�R���Y�Ғ��i2000�j�w���ȏd�v�p��300�̊�b�m���x�i�d�v�p��300�̊�b�m���U�j�ł��B�{���T�́C�^�C�g���͈���Ă��܂����C��{�I�ɂ͂����́w���ȏd�v�p��x�̉����łɂ�����܂��B
�@�{���T�̍ő�̓��F�́C���l���̎��M�҂������C���ꂩ��̂킪���̗��ȋ��猤�������[�h���钆���̌����҂𒆐S�Ƃ��C�V�i�C�s�̎��̌����҂�����������M�w�ł��邱�Ƃł��B
�@�Ƃ���ŁC���E�I�Ɍ���ƁC�����n���h�u�b�N�iHandbook�j�́C��������������Ă��܂��B���T�iEncyclopedia�j�́CR. Gunstone���Ғ��҂Ő��E���̑����̌����҂��ւ��C2015�N��Springer���甭�����ꂽEncyclopedia of Science Education������܂��B�{���T�́C����قǂ̑咘�ł͂���܂���B�܂��C�c�O�Ȃ��ƂɁC���̎��T�̓��{�l���M�͑�������܂���B�������Ȃ���C���̓x���������{���T�́C���{��i���ŏ��w�Z�����w�@�܂Ŋw�ׂ鍑�́C���E�ł���L�ȑ��݂ł��j�ŏ�����Ă���C�����҂��狳�t�C�����ċ��t��ڎw����w���܂ŕ��L���ǎ҂�ΏۂƂ��Ă��܂��B�{���T�̎��M�҂�{���T�ŗ��ȋ���ɂ��Ċw�����̌����҂��C�₪�āC���ۓI�ȗ��ȋ��玖�T���̃v���W�F�N�g�ɎQ�������邱�Ƃ����҂��Ă��܂��B���̂��Ƃ��C�킪���̗��ȋ��猤���̐i���ɂȂ�܂��B�{���T�́C���̂��߂̓��发�ƈʒu�Â��Ă��悢�ł��傤�B
���ȏd�v�p�ꎖ�T�̗��p�̎d��
�@�{���T�́C����܂ł̑O�Q���́w���ȏd�v�p��x�Ɠ����悤�ɁC�\�����̌f�ڏ����ł͂Ȃ������̈斈�ɋ敪���Ă��܂��B�O�Q���̓^�C�g���̒ʂ藝�ȂɊւ���300�̗p�ꂪ�f�ڂ���������Ă��܂����C�{���T�ł̗p��̐��͂��̔����ȉ��ł��B�������Ȃ���C�p��̐��͔����ȉ��ł����C�O�Q�����e�p��P�łł������̂ɑ��āC�{���T�͔{�̂Q�łł��ڍׂɗp��̉��������Ă���܂��B���̂��߁C�P�Ȃ�p���������ɂƂǂ܂炸�C�����̗��j��g�����h�C���H�ւ̎��������܂܂�Ă���܂��B
�@�܂��C����I�ȏ��݂̍���Ƃ��āC�e�p��̖��ɂ͕������L�ڂ���Ă��܂����CQR�R�[�h���g���C�e�p��̑S�Ă̕������{���ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�ǎ҂̊F����́C�������X�g�ɋL�ڂ���Ă��鏑�Ђ�_�������������g�Ŏ�ɂƂ�C������ǂ�ł݂邱�Ƃ͌����͂��Ƃ��C���X�̎��H�ł��C�����̍l��������薾�m���C���邢�͋�������C�l��������X�̎��H�ɐ[�݂������Ă���ł��傤�B
�ӎ�
�@�Ō�ɂȂ�܂������C�{���T�̊�悩�玷�M�C�o�łɎ���ߒ��łS���̗D�G�ȕҒ��҂ł���}�g��w�����D��搶�C�{���w������P�搶�C�L����w���Y���搶�C�}�g��w�R�{�e�q�搶�i�\�����j�ɂ͑�ς����b�ɂȂ�܂����B�L���Ďӈӂ�\���܂��B
�q�����r
傒J�Ďi�E�ؑ��m�וҒ��i1981�j�w���ȏd�v�p��300�̊�b�m���x�i���ȋ���̊�b�p��V���[�Y�j�����}��. �^Gunstone, R. (Ed.). (2015). Encyclopedia of science education, Springer.�^�����d�a�E�H�R���Y�Ғ��i2000�j�w���ȏd�v�p��300�̊�b�m���x�i�d�v�p��300�̊�b�m���U�j�����}���D
�@�@2025�N�W���@�@�@�ďC�@�^�����@�N�v
-
 �����}��
�����}��














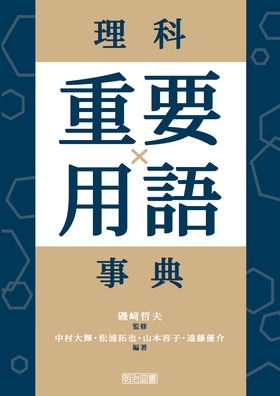
 PDF
PDF

