- はじめに
- 1章 1人1台端末時代の音楽室セッティング
- GIGAスクール構想で音楽室はこう変わる!
- 誰でもできるスタートガイド
- 1人1台端末時代,どんな機器がある?どんなことができる?
- [ハード]
- タブレット
- スマートフォン
- PC(パソコン)
- スクリーン/プロジェクター/大型テレビ/電子黒板
- スピーカー
- 書画カメラ/ドングル・レシーバー/MIDIキーボード
- どんなふうに接続したらいいの?
- [ソフト]
- インターネット/動画サイト/アプリ
- [OS]
- iOS/Windows/Chrome OS
- Column1 録音のプロに聞く よい音で録る秘訣
- 2章 ICTで魅力的に変わる音楽授業スタンダード
- 収録アプリ一覧早見表
- 便利になる!楽になる!ICTを活用した音楽授業マネジメント
- 01 演奏を録画してよりよい表現を目指そう
- 02 音当てクイズをつくろう
- 03 演奏の創意工夫はどんどん書き込んで保存しよう
- 04 プレイリストを作成して瞬時に音楽を再生しよう
- 05 うまくなろう!YouTubeで個人練/パート練
- 06 Jamboardを使って話し合いを活性化しよう
- 07 スライドや写真に付箋の目隠しをしよう
- 08 楽譜やパート譜を作成しよう
- 09 音源を編集して鑑賞の集中度を上げよう
- 10 音源からボーカルを取り除いて伴奏音源をつくろう
- 11 スキャナ・アプリで資料をどんどん取り込もう
- 楽しい!学びが深まる!ICTを活用した音楽授業アイデア
- [導入・常時活動]
- 12 ICTで音楽室の雰囲気を盛り上げよう
- 13 タブレットを使って音楽を学ぼう
- 14 バーチャル楽器サイトを活用しよう
- 15 音楽の世界を広げよう
- [歌唱]
- 16 スクリーン上で歌詞と伴奏を連動させよう
- 17 自分の歌を伴奏に合わせて録音しよう
- 18 ハモリを身につけよう
- 19 先生や友達とデュエット動画を撮影しよう
- 20 ゲーム感覚で謡を体験しよう(中学)
- [器楽]
- 21 お手本をもとにリコーダー二重奏にチャレンジ!
- 22 ステップバイステップでうまくなろう
- 23 リコーダーの運指を覚えてステップアップ!
- 24 自分の篠笛演奏を客観的に振り返ってうまくなろう(中学)
- [音楽づくり]
- 25 ◯◯のチャイムをつくろう
- 26 民謡のお囃子をつくってみよう
- 27 音楽で学ぶプログラミング的思考
- 28 「Scratch」で音楽のプログラミング
- 29 サンプリング音源で音楽をつくろう
- 30 循環コードで旋律をつくろう(中学・創作)
- [鑑賞]
- 31 音楽を「見える化」して聴いてみよう
- 32 曲の部分部分を確かめながら鑑賞しよう
- 33 変奏曲の順番を考えよう
- 34 Google Jamboardで音マップをつくろうGoogle Formsで感想を集計しよう
- [伝統音楽]
- 35 タブレットでお箏の練習をしよう
- 36 アプリで伝統音楽
- [行事等]
- 37 思い出動画をつくろう
- 38 音楽発表会を演出しよう
- 39 僕たちの思い出を残そう!
- [特別支援]
- 40 音の鳴る絵をつくれるアプリ「paintone+」で自分だけのデジタル楽器づくり
- 41 画像検索をしてミュージックビデオをつくろう
- Column2 鍵盤ハーモニカ奏者がハマった多重録音動画制作の魅力
- [役立ちHP]
- 42 学習支援コンテンツ(教育芸術社)
- 43 まなびリンク(教育出版)
- 44 伝統音楽デジタルライブラリー(洗足学園音楽大学)
- 45 文化デジタルライブラリー(日本芸術文化振興会)
- 46 楽器解体全書(ヤマハ)
- 47 NHK for School(NHK)
- 48 ピアノニマスの鍵盤ハーモニカレッスン
- 49 Percussion & Piano FLOWER BEAT
- 50 音楽授業×ICT リンク集
- Column3 ICTと音楽の未来
- 執筆者一覧
- ※本書に収録している二次元コード等の情報は,執筆当時のものです。
はじめに
1人1台端末の時代になって,音楽の授業や子どもの学びは急激に変化しているように見えます。しかし,これまでの先生方の教育や子どもの学びが変わるわけではありません。今までの実践の蓄積があるからこそ,タブレットを使う実践は,音楽的により深い学びの達成が可能になります。このことを念頭において,タブレットを音楽授業に活用するよさを私なりにいくつか挙げてみます。
・楽譜の知識や演奏の技術がなくても音楽を表現できる。
・現在進行形の音楽シーンにつながることができる。
・音楽文化を知るだけではなく,自分たちで音楽をつくることができる。
・一人一人のペースで学ぶことができ,学んだことをクラスと容易に共有できる。
・学びの軌跡の一つ一つを残すことができる。
タブレットは,子どもの心に鳴り響く音楽を表出する手助けをします。また近年,多くのアーティストがタブレット1台でヒット曲をつくっているのはご存知の通り。クラシックや伝統音楽の世界でもマルチメディアの技術を使った新しい試みが見られます(そのいくつかを本書でも紹介しています)。このようにタブレットは,子どもたちの想いを具現化し,またリアルな音楽の世界とつながることを可能にします。
タブレットを操作する子どもを観察していると,「こんな風に動かせる」とか「こんなこともできる」といった思いがけない発見をよく見ます。これは「習うより慣れろ」の精神です。タブレットを授業に使う際は,この思考が助けとなるかもしれません。本書では,たくさんのアプリと50の活用例を紹介しました。本書を出発点にして,先生自らアプリを楽しみながら試してみてください。これまでの教育実践の経験とつながって「○○の活動に使えそうだ」という発想がきっと生まれるでしょう。また,音楽を知るためのサイトをたくさん紹介しました。これらのサイトを起点にして,より多彩ですばらしい音楽の世界につながることもできるでしょう。
2022年1月 /瀧川 淳
-
 明治図書
明治図書- ICTを活用した授業の入門書として、とても分かりやすかったです。購入してよかったです。2023/12/1550代中学校教諭
- PDF化されているので、様々な端末で見られて便利。2023/7/230代・小学校教員














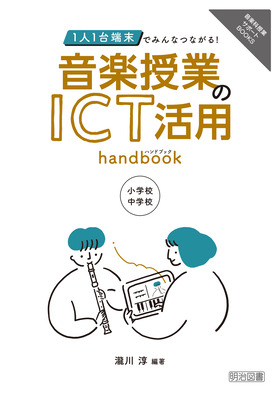
 PDF
PDF

