- はじめに
- 1 社会科で育む自立した学習者と個別最適な学び
- 1 自立と自律の違いとは?
- 1 自立した学習者を育てる
- 2 「自立」と「自律」
- 3 補完し合う関係
- 2 なぜ社会科で「自立した学習者」を育てる必要があるのか?
- 1 社会を「知る」だけでなく「関わる」ことが求められる
- 2 「個別最適な学び」を社会とつなげる必要がある
- 3 「この子らしい学び」と「社会科らしい学び」の往還が必要
- 3 「自立した学習者」を育てる教師の条件は?
- 1 どの子も主体的に学ぶ有能な学習者であるという立場に教師が立つ
- 2 教師の知識や技術を子どもに譲り渡す展望をもつ
- 3 手渡すべき知識や技術を教師が身につけ,磨く
- 4 教室に物理的心理的「縁側」をつくる
- 5 教師自身が自立的な学習者であり続ける
- 2 「個別最適な学び」の基礎基本
- 1 「個別最適な学び」とは?
- 2 「『個』をみること」とはどういうことか?
- 3 子どもを見取るために必要なことは何か?
- 4 子どもをさぐるためにどのように記録をとればよいのか?
- 5 なぜ子どものエピソードで語ることが大切なのか?
- 6 子どもによる記録はどのように残したらよいのか?
- 7 子どもの見取りをどう活かすことができるのか?
- 8 授業UDとUDLの違いは?
- 9 授業UDの教材論とは?
- 10 授業UDの課題と展望は?
- 11 個の学びを豊かにする教材をどのようにつくるのか?
- 3 「個別最適な学び」×社会科授業デザインのポイント
- 1 社会科として大切にしたい思考は何か?
- 2 個別最適な学びを進めるための第一歩は何か?
- 3 教師の役割はどのように変わったのか?
- 4 個別学習のときに教師は何をしている?
- 5 単元はどのようにデザインすればよいか?
- 6 単元構想の捉え直しはできる?
- 7 指導案はどう書けばいい?
- 8 「受けの学習計画」とは何を意味するか?
- 9 「個別最適な学び」に必要な一斉授業の技術は?
- 10 自律的な学習者を育てるにはどうすればよいのか?
- 11 自律的な学びを進めるための「第一歩」は何か?
- 12 子どもが学びを進めるための環境をどう整える?
- 13 子どもに任せる塩梅の見極めとは?
- 14 活かす場面でなぜ「この子らしさ」が出るのか?
- 15 自立した学習者を育てるためになぜ「リアル」が必要?
- 16 「自己決定的学習モデル」の中学年事例とそのポイントは?
- 17 若手教師への助言はどうすればよいのか?
- 18 学級の「文脈」はどのようにつくられるのか?
- 19 失敗談はどんなものがあるか?
- 4 「個別最適な学び」子どもの育ちと評価のポイント
- 1 子どもが自己選択,自己決定する機会を増やすには?
- 2 子どもが自己評価することは大切なのか?
- 3 「活動あって学びなし」にならないようにするには?
- 4 自分で学びを進めるときに何が大切なのか?
- 5 子どもの側からつくる問いとはどういうこと?
- 6 問いの醸成には「間」が必要?
- 7 子どもが「問い」をもって学習を進めるには?
- 8 子どもはどのようにして「学び方」を学ぶのか?
- 9 子どもはどうやって仮説を立てられるのか?
- 10 子どもにどのような言葉を投げかけているか?
- 11 この子「らしい」発言を引き出すには?
- 12 「この子」が動き出したときの例はあるか?
- 13 子どもが目にはみえない意味や特色を見出すには?
- 14 子どもの「思考の癖」をどう見出すのか?
- 15 この子「らしい」追究を進めるには何が大切か?
- おわりに
はじめに
本書は,「個別最適な学び」シリーズの第4作目となる「Q&A編」です。
これまで,理論編(青版)ではその背景と思想を,実践編(赤版)では授業づくりの工夫を,事例編(黄版)では全国の先生方の実践例を紹介してきました。それからの巻で積み重ねてきた問いや手ごたえをふまえ,本書では現場の先生方から寄せられたリアルな問いに応えるかたちで内容を構成しています。なお,本書のもとになっているのは,2022年度から2024年度にかけて月刊誌『社会科教育』で継続的に連載してきた内容です。連載で扱ったテーマを加筆・修正し,再構成しました。
第1章では,「個別最適な学び」の根っこにある考え方をあらためて整理しました。ここでは,個別最適な学びの目標とは何か。なぜ今,自立した学習者を育てる必要があるのか。そのために教師にはどのようなまなざしや条件が求められるのか。そうした問いに立ち返っています。さらに「自立」と「自律」の違いを丁寧に考えながら,社会科における学びの“リアル”との接点をどう設計するか,「この子らしい学び」と「社会科らしい学び」が交差する場を,どう生み出していくのかを掘り下げました。
第1章だけはQ&A形式ではなくやや理論的な構成になっていますが,それには理由があります。第2章以降の問いをより深く読み解き,日々の授業実践に活かしていくためには,「何をめざしているのか」という立ち位置を確認する“足場”が必要だと感じたからです。
第2章から第4章では,現場の先生方からいただいた問いに一つずつ応答するかたちで,「個別最適な学び」の実践に必要な視点を掘り下げました。
第2章では,個別最適な学びの「基礎基本」として,そもそもそれがどういうものなのか,そして「個をみる」とはどういう営みなのかを問い直しました。教師の記録のあり方,子ども自身による記録,エピソードで語る意味など,“見る”と“残す”という行為の意味を,日常実践の中に位置づけ直そうと試みています。
第3章では,社会科における授業デザインの視点から,思考を育てる単元の構想,教師の関わり方の変化,教室環境や子どもとの関係づくりなど,授業づくりの土台となる問いを中心に取り上げました。その中でも「教師がどう立ち位置を変えれば,子どもが動き出すのか」という視点は,数多くの現場からの共通の悩みでもありました。
第4章では,子どもの「育ち」と「評価」をめぐる問いに応答しています。問いをもつ力や仮説を立てる力をどう育てるか,自己決定の機会をどう保障するか,そして子どもの「思考の癖」や「らしさ」をどう見つけ,価値づけていくのか。教師の言葉がけ,問いの“間”,子どもの反応など,学びの繊細なプロセスを捉え直す章となっています。
全体を通して大切にしたのは,読者とともに考える構えです。正解を示すのではなく,現場で日々揺れながら考える教師のまなざしを共有したいと考えました。読者自身が,自分の問いに向き合うきっかけとなることを願っています。
「個別最適な学び」という営みは,完成された答えをもつものではありません。子どもとともに揺れながら,問いながら,よりよい学びのかたちを模索し続けるものです。
本書が,その揺らぎの中に立ちあらわれる“気づき”の一つとなれば幸いです。読者のみなさんの中に,新たな問いや確信が芽生えるきっかけとなれば,これ以上の喜びはありません。
/宗實 直樹














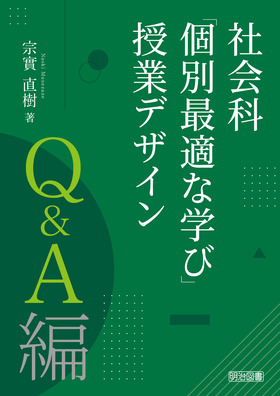
 PDF
PDF


宗實先生が今も磨き続けていることが伝わってくる1冊でもあります。
あとはQA形式でコンパクトにまとめられているので読みやすいです。