- はじめに
- 第1章 中学校理科における個別最適な学び・協働的な学び
- 1 中学校理科の学習指導要領の構成
- 2 理科の目標のとらえ方
- 3 指導の個別化・学習の個性化
- 4 個別最適な学び
- 5 自己決定と自己調整
- 6 協働的な学び
- 7 探究的な学び
- コラム 旧来型のチョーク&トークの教育実習
- 第2章 自己決定を核とした個別最適な学びを目指した実践事例
- 1 観察対象を選択肢の中から選ぶ
- (第1学年 生物領域 生物の観察と分類の仕方)
- 2 観察対象を自由に選ぶ
- (第1学年 地学領域 地層の重なりと過去の様子)
- 3 単元内自由進度学習を行う
- (第1学年 物理領域 力の働き)
- 4 実験計画の立案で自己決定を促す
- (第3学年 化学領域 化学変化と電池)
- コラム 生徒の行動を含めた授業構成
- 第3章 自己調整を核とした個別最適な学びを目指した実践事例
- 1 やり直しレポートを作成する
- (第2学年 物理領域 電流)
- 2 シミュレーション教材を活用する
- (第3学年 生物領域 生物と環境)
- 3 教材を自由に選択して使える環境を整える
- (第3学年 地学領域 天体の動きと地球の自転・公転)
- コラム 授業改善に役立つICT
- 第4章 相互啓発を核とした協働的な学びを目指した実践事例
- 1 バイキング形式で観察・実験計画を立てる
- (第1学年 化学領域 物質のすがた)
- 2 条件制御を意識して実験計画を立てる
- (第1学年 物理領域 力の働き)
- 3 作成したレポートの相互評価をする
- (第2学年 化学領域 化学変化)
- 4 共有機能を利用して観察・実験計画を立てる
- (第2学年 生物領域 植物の体のつくりと働き)
- 5 協働的に資料の情報を分析する
- (第2学年 地学領域 日本の気象)
- 6 自分の意見に自信度を設定する
- (第3学年 物理領域 力のつり合いと合成・分解)
- 7 グループレポートを作成する
- (第3学年 地学領域 太陽系と恒星)
- コラム ICTの波
- コラム 個別最適な学びを行う意味
- おわりに
はじめに
中央教育審議会(以下,中教審)の答申「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す,個別最適な学びと,協働的な学びの実現〜」は,令和3年1月に明らかになりました。その当時の学校現場は,収束が見通せないコロナ禍の対応に追われ,それどころではありませんでした。しかし,未来を見据え,考え抜かれた提案がいくつも記されているこの答申は,その後の教育界に,じわじわと浸透し始めています。
数ある提案の中でも,「『個別最適な学び』と『協働的な学び』を一体的に充実し,『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業改善につなげていく」という部分は,特に意義深いものです。中でも,答申で指摘されるまでもなく,実現すべきだと考えてはいる「個別最適な学び」という文言が,現場教師の胸に刺さります。「個別最適な学び」は新しい文言ですが,「指導の個別化・学習の個性化」であれば,実は,昭和の時代からすでに学校現場で唱えられていました。以前から大切にすべきだということはわかっていました。ただ,納得できるような形には,なかなかできなかった…答申は,そこを突いた形です。本書のテーマともつながっています。
理想的な授業の形態として,「できればやってみたいが,現状では難しい」というのが,教師の本音です。「40人学級の生徒集団では難しいが,少人数学級が導入されれば,ハードルが下がる」と考えている教師もいるでしょう。実現を目指したいのです。
その一方で,「個別最適な学び」との一体的な充実を求められている「協働的な学び」は「何とかなる」という教師が多いようです。「個別最適な学び」に比較すれば,実現の可能性は高いでしょう。ただ,「協働的な学び」と「個別最適な学び」との一体的な充実が求められており,「主体的・対話的で深い学び」を実現することで,その成果が表れます。
また,本書では,ICTを活用した事例をいくつも掲載しました。「単元内自由進度学習」の事例も掲載しました。いずれも個々の生徒へ支援することが前提で,確かに,一斉授業より,授業の準備が必要になります。観察・実験の指導のスキルにさえ慣れていない若い教師には,なおさらハードルが高いでしょう。
できない理由,やれない言い訳を並べても,前には進めません。
今の学校で無理なくできることは何か…具体的な事例を通して明らかにしたいと考えました。
それが,本書の刊行のねらいです。
第1章では,個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実させるにあたり,中学校理科での背景を明らかにしました。
第2章以降では,14の具体的な実践例を,解説とともに紹介しました。
特別支援が必要な生徒を含め,全ての生徒が有能な学び手であり,学びの環境が整いさえすれば,自ら進んで学んでいきます。
その実現に,本書が役立てば,幸いです。
2025年盛夏 /山口 晃弘
-
 明治図書
明治図書- 具体的事例が豊富で、活用しやすい構成でした。事例にも筆者が載っているとより活用できると思いました。2025/11/1540代・中学校教員














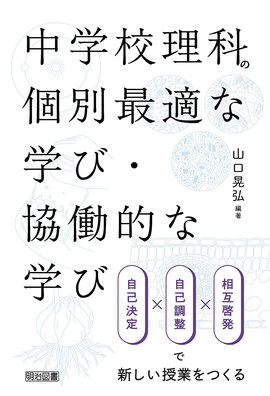
 PDF
PDF

