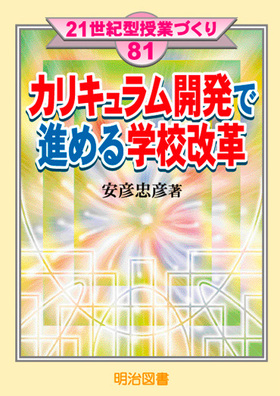- まえがき
- はじめに ─「カリキュラム時代」の再来
- Ⅰ カリキュラム開発の基礎原理
- ─学校と教師の意識変革の必要─
- 一 「カリキュラム開発」に対する社会的要請と学校の責任
- 二 「カリキュラム・デザイナー」としての教師
- 三 カリキュラム開発の原理─カリキュラムづくりの基礎―
- 四 カリキュラムの分析・批判─問題点の析出と開発上の留意点─
- Ⅱ カリキュラム開発の方法
- ─教師の役割変化と力量向上─
- 一 カリキュラム開発の基本方針─プランニングとデザインの総合─
- 二 カリキュラム開発の方法
- 三 カリキュラム開発の基本的方向
- ・具体例─太宰府市立国分小学校・滋賀大学附属学校園─
- (1)太宰府市立国分小学校の場合
- (2)滋賀大学教育学部附属学校園の場合
- 四 カリキュラムの最近の類型化と特色づくり
- ・具体例─「総合的学習」のカリキュラム開発で教師が変わる!─
- (1)江南市立古知野東小学校の場合─
- 五 カリキュラム開発における店ハイブリッド・モデル点の提唱
- ・具体例─学校全体のカリキュラム開発で教師が変わる!─
- (1)安城市立桜町小学校の場合
- Ⅲ カリキュラム開発を支える経営体制
- ─教師・学校・保護者・地域の分担と協力─
- 一 カリキュラム開発のための組織づくり─体制・経営・評価・改善─
- 二 カリキュラム経営の位置と重要性
- 三 カリキュラム開発の主体の確認と拡大
- 四 カリキュラム開発の主体の拡張と評価対象の拡大深化
- カリキュラム評価の必要性
- ─学校と教師も評価の対象─
- 一 カリキュラム評価の恒常化─不断の改善のために─
- 二 カリキュラム評価の諸方法
- 三 カリキュラム評価の具体的な進め方
- 四 カリキュラム評価の活かし方
- 終わりに ─カリキュラム開発で進める学校改革─
- あとがき
まえがき
本書は、月刊誌『現代教育科学』二〇〇〇年六月ごうから二〇〇二年三月号まで、一年半連載した「カリキュラム開発で学校と教師が変わる!」に手を加え、一冊にまとめたものである。
現在、学校はどこも元気がない。学校が世の中を引っ張っていく、または新しい世の中をつくる時代ではなくなり、むしろ国民から信頼を失い、教師は見放されているかのようである。それほど、学校に対する社会の目は厳しい。しかし、その社会の方に問題がないのかと言えば、そうとは言えない。より冷静で丁寧な議論が必要とされるゆえんである。
新学習指導要領により、昨年度から小・中学校で始まった教育課程の改革は、本年度から高校も加わり、その結果、一層その効果に疑問が強まって、小・中学校については来年度から修正できるような、学習指導要領の部分改訂の作業が進んでいる。
しかし、実態はすでにこのような動きを可能にするほど「規制緩和」の流れが強まり、実は現在の段階でも、かなり学校の実情、子どもの実際の姿によっては、個々の学校レベルで柔軟に対応することができるようになっている。それほど学習指導要領が大綱化、柔軟化しているのである。変わらないのは、むしろ地方教育委員会や各学校(の教師)であると言ってよい。地方教育委員会はもちろん、学校も教師も変わらねばならないのである。
ではこれらの動きに対して、教師一人一人はどのように変わればよいのか、また今後の学校での教育活動を、何を土台にして、何を目指して、何に焦点を当てて変えていけばよいのかについて、誰も明確に述べていない。これまでの教育とこれからの教育のどこを、どう変えればよいのかについて、教師の認識は明瞭にならず、展望が開けている様子が見られない。どこか五里霧中のところがある。
このような、漠然とした不安な状況のまま教師が実践を続けることは、決して望ましいことではない。教師をサポートしたいと思っている筆者のようなものにとって、教師こそが実践を通して事実をつくっているのだ、という自負と責任を強くもってほしいし、教師に元気を出してもらいたいのである。それには、教師の認識を明瞭にすることのできる助言や示唆は何かを考え、望ましい実践に少しでも役立ててもらえる提言をしたい。本書は、最近の「カリキュラム開発」という仕事を通して、それを試みようとしたものだと言ってよい。
新学習指導要領が目指している「学力観の転換」については、それが記憶重視の学力観から思考重視の学力観へ「重点移動」することと考えるならば、誰も反対することはない。問題は、この「方向」は妥当だが、「方策・方法」が適当ではない、ということにある。形成すべき「学力」と「人格」の中身に直接対応する部分が「カリキュラム」であると言えようが、この意味で、学校で「カリキュラム開発」の作業が正面から求められるこれからの教師に、少しでも役立つようにとの思いで書いた。ただ、その作業がそう簡単なことでないことは十分承知しており、だからこそ学校が「改革」されねばならないとも、言わねばならないのである。
現在の学校は改革・改変が必要なほど、教師に期待がかけられているのであり、「教育の専門職者」としての実力が試される時代になったと言えよう。中央と地方の教育行政担当者は、教師のこの種の活動を支援し強化する方向で、積極的に援助する方針を明確にすべきである。教師がこの方面の仕事に本腰を入れて取り組むことができるように、物的人的条件整備を惜しまないでほしい。それなくしては、学校も教師自身も、容易に変わることはできないであろう。
なお、用語の「カリキュラム」について一言する。一般に教育行政用語としては「教育課程」という用語が使われる。しかし、「カリキュラム」という用語も徐々に復活して、中央の教育行政担当者でも、この語を口にすることが増えている。それは、やはり従来の「教育課程」という用語だけでは論じられない部分が増えてきたことによる。それだけ、教育の事実が単純ではなくなっているのである。「教育課程編成」とは言えるが、「潜在的教育課程」とは言えず「潜在的カリキュラム」である。「教育課程」は計画段階の、しかも公式の部分だけを言うのが普通であり、「カリキュラム」は学習の結果を含む、非公式の部分まで入る用語であると言ってよい。現在では、このレベルまでを含まないと議論ができない状況にあるのだと言ってよい。
本書が、学校で教師一人一人に、理論的でありつつ、実践的にも役立つものになっている、と実感してもらえると嬉しい。それにより、教師が専門職者として自信をもつことができれば、実践家を応援するものとして何よりの幸せである。
二〇〇三年 盛夏 著 者
-
 明治図書
明治図書