- はじめに
- 1 平成29年版学習指導要領から
- 2 社会的な見方・考え方
- 3 本書の使い方
- 4 教材開発の極意
- 第1章 「見方・考え方」を鍛える! 小学3年社会科教材探究ワークシート
- 1 町へ出かけよう!(町探検)
- 2 校区のチラシ地図から(地図の見方)
- 3 床屋さんの地図記号は?(わたしたちの町)
- 4 農家の工夫を見抜け!(農家の仕事)
- 5 コンビニのヒミツをさぐろう!(店で働く人)
- 6 デパートのナゾ?(店で働く人)
- 7 どこから来たの?(他の地域とのつながり)
- 8 ザ・火消し!(消防)
- 第2章 「見方・考え方」を鍛える! 小学4年社会科教材探究ワークシート
- 1 2つの断面図で富士山を知る!(断面図の学習)
- 2 マンホールの謎を科学する!(下水処理の学習)
- 3 水はどうやって流れてくるの?(上水道の学習)
- 4 プラグの向こう側!(電気の学習)
- 5 備えあれば憂いなし!Ⅰ(自然災害)
- 6 棚田を拓くⅠ(郷土の開発)
- 7 棚田を拓くⅡ(郷土の開発)
- 8 伝統的工芸品とは!(伝統工芸の学習)
- 第3章 「見方・考え方」を鍛える! 小学5年社会科教材探究ワークシート
- 1 Myさくいんを作ろう!(地図の見方)
- 2 日本の重心はどこ?(国土の様子)
- 3 日本一の植木スイカ!(農業)
- 4 釣り具から始めよ!(水産業)
- 5 原油はどこから,どうやって?(エネルギー)
- 6 新聞社の仕事!(情報産業)
- 7 新聞vs.テレビvs.ネット(情報産業)
- 8 水俣病という公害について(公害)
- 9 備えあれば憂いなし!Ⅱ(自然災害)
- 第4章 「見方・考え方」を鍛える! 小学6年社会科教材探究ワークシート
- 1 日本国憲法を読んでみよう!(日本国憲法)
- 2 『蒙古襲来絵詞』に挑戦しよう!(鎌倉時代)
- 3 ザ・シュガーロード!(戦国・江戸時代)
- 4 米価から飢饉や事件を読み取る!(江戸時代)
- 5 地租改正は増税だった?(明治時代)
- 6 原子爆弾は日本人を救ったのか?(戦争の世の中)
- 7 どこのコーラ?(世界の中の日本)
- 8 JICAから世界を知る!(世界の中の日本)
- おわりに
はじめに
1 平成29年版学習指導要領から
平成29年版学習指導要領が提示された。平成20年版学習指導要領からすると,かなり大きな変革となっていると感じる。それは,目標を比べてみただけでも分かるだろう。
平成20年版学習指導要領 社会科目標
社会生活についての理解を図り,我が国の国土と歴史に対する理解と愛情を育て,国際社会に生きる平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を養う。
平成29年版学習指導要領 社会科目標
社会的な見方・考え方を働かせ,課題を追究したり解決したりする活動を通して,グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の形成者に必要な公民としての資質・能力の基礎を次のとおり育成することを目指す。
「社会的な見方・考え方」という視点が登場し,問題解決学習をやると目標に明記されている。その視点とは,「社会的事象を位置や空間的な広がり,時期や時間の経過,事象や人々の相互関係に着目して捉え,比較・分類したり総合したり地域の人々や国民の生活と関連付けたり」する見方・考え方としている。
さらに,「次のとおり」として,3項目が追加されている。
(1) 地域や我が国の国土の地理的環境,現代社会の仕組みや働き,地域や我が国の歴史や伝統と文化を通して社会生活について理解するとともに,様々な資料や調査活動を通して情報を適切に調べまとめる技能を身に付けるようにする。
(2) 社会的事象の特色や相互の関連,意味を多角的に考えたり,社会に見られる課題を把握して,その解決に向けて社会への関わり方を選択・判断したりする力,考えたことや選択・判断したことを適切に表現する力を養う。
(3) 社会的事象について,よりよい社会を考え主体的に問題解決しようとする態度を養うとともに,多角的な思考や理解を通して,地域社会に対する誇りと愛情,地域社会の一員としての自覚,我が国の国土と歴史に対する愛情,我が国の将来を担う国民としての自覚,世界の国々の人々と共に生きていくことの大切さについての自覚などを養う。
このように,従来の目標より具体的な観点が提示されている。
2 社会的な見方・考え方
そこで,本書では,上記の新しい指導要領に鑑み,「社会的な見方・考え方」を身につけられるようなワークシートを作成してみた次第である。
社会科は,他の教科と違って,かなり「地域性」を帯びてくるという側面がある。以前から同心円的拡大方式と呼ばれてきているところである。
例えば,教科書では,日本全国の特色ある地域を1つ選んで,そこを中心に記述してある。「低地のくらし」という小学5年の単元があったとすると,A社は岐阜県や三重県の「輪中」を取り上げるという具合である。しかし,学習する子が住んでいる地域には,輪中はないかもしれない。低地さえないかもしれない。そんな時,次の2つのやり方が考えられる。
X:教科書の輪中を取り上げて(低地の代表として),学習する。
Y:副読本などで取り上げてある地元あるいは近くの低地を学習する。
Xでは,「輪中から日本の低地が見える」という仕組みになる。輪中堤は,どこの低地にでもあるものである。さらには,「水屋」はないかもしれないが,自宅を道路より高く造成するというパターンはよく見受けられるところである。つまり,「◯◯から□□が見える」という社会的な見方・考え方が重要である。このワークシートもそういう見方で使って頂けると有り難い。
Yに関しては,例えば熊本には低地がある。それは,特に八代平野などを中心とした「新田開発」でつくられた平野である。あるいは,隣接県になるが,佐賀平野のクリークがある。どこを取り上げるかは,教師次第であろう。
さらには,「往復運動」も必要である。図2にあるように,近くの八代平野を見て,遠くの輪中を見たりする学習活動である。反対に,遠くの輪中を学習して,熊本はどうだろうという学習設定である。要するに,
遠近両用メガネを脳に身につける必要があるということだ。
これは,地理学習だけではなく,歴史学習にもあてはまる。例えば,江戸幕府の学習(中央史)をしながらも,地元の肥後藩(地方史)はどうだったのだろうということである。こうして,共通点や相違点を見いだしていく学習も,新学習指導要領が求めているところであると感じている。
要は,新学習指導要領のいう,
「社会的な見方・考え方」を働かせることである。
3 本書の使い方
社会科が教科書一辺倒では学習できない所以がおわかり頂けたかと思う。特に,小学3年・4年の学習では,地域を扱うだけに,各地で副読本が製作されているはずである。学習内容や発達段階から,その地域の学習は外せない状況でもある。
そこで,本書の登場である。こちらは副読本ではなく,副ワークシートという存在である。場合によっては,読者の地域では使えないものもあるだろう。上記の理由から当然である。そのような場合には,その地域の写真や文章に差し替えたり,少しアレンジをしたりして頂ければ幸いである。もちろん,どこの地域でもあてはまるというものもある。
本書は各節,2部構成となっている。1部が解説的ページで,2部が児童配布用ワークシートとなっている。
解説部は,次のような節で構成している。
【ワークのねらい:つけたい資質・能力】 (1)から(3)まで,学習指導要領の目標に従って,テーマに関するものを順に記述してみた。
【鍛えるポイント:社会的な見方・考え方】 各テーマ(ワークシート)に関連して,どんな見方や考え方を育成していけばよいかについて,記述してみた。
【展開と指導の流れ】 ワークシートを使う際の授業の流れを記述してみたが,これは学級や地域の実態によって変更可能である。
【解答例と評価のポイント】 解答例を中心に記述した。子どもの意見は様々だろうから,解答例と似た,大まかなことを書いてあればそれでよしというような,評価のポイントも示した。
【教材開発の極意】 こんな授業も考えられる,あるいは,こんな教材も開発できるというようなヒント(極意)や付随事項を記述してみた。
ワークシート部は基本的には1枚ものだが,テーマによっては,複数ページにわたるものもある。ワークシートのテーマ名は,子ども向けにしてある。
ワークシートを授業で使用する際には,シート全面を渡してしまうと,先が見えたり,答えがわかったりする場合もある。そんな時は,全てを印刷した後に,部分的に切り離して,順次,配付していくという形にするとよいだろう。授業終了の際は,ノートに配付順に貼っていくという作業も必要になる。紛失してしまえば,学習の記録がなくなるからである。面倒でも,地道にさせていきたいものである。社会科に,ハサミとのり,色鉛筆は必需品である。
本書の土台は,中心テーマである「社会的な見方・考え方」を育成するワークシートということである。
例えば,歴史的絵画を見る場合を想定してみよう。
ただ単に絵画資料を見ても,歴史的事象を見抜いていくことは難しい。例えば,絵画の細部を見ていくやり方がある。その「絵画の見方」を養成できるワークシートにもなっている。
これは,単に絵画の見方にとどまらず,例えば,学習指導要領が重んじている課題作成の仕方,見学の仕方,写真の見方,等々に関係することでもある。そのような「見方」が身につくワークシートに仕上げているので,特に「仕方・見方」の場合には繰り返し使って頂ければと思う。小学3年の課題設定の仕方のワークシートを,5年で使っても何ら問題はない。そのように,繰り返し使っていくことで,「社会的な見方・考え方」が身についていくと考える。
4 教材開発の極意
ワークシートは,自分が使いやすいようにアレンジするのがベストだと考える。担当する子どもが違えば,教える教師も違う。当然,住んでいる地域が違うし,使用している教科書も違う。だから,できれば,自分で作成するのが一番である。このワークシートをその土台として利用して頂くということも想定している。
前述したように,各テーマの終末に「教材開発の極意」という節を設けている。地域性の強い社会科だからこそ,教材開発は欠かせないだろう。その極意というものを付け加えた次第である。
例えば,長崎から北九州までの肥前街道というのが江戸時代にあったが,ここは今「シュガーロード」として売り出し中である。実際に,当時,「砂糖の道」であったのだ。平戸で貿易をしたポルトガル人が「南蛮菓子」を伝え,鎖国後は場所を長崎は出島に移して行われた。そこでは,中国人やオランダ人が砂糖を持ちこみ,それは京都や江戸へと運ばれていった。そのおこぼれが肥前街道を満たし,菓子が作られてきたという歴史がある。
ここを本書でワークシートとしても掲載しているが,このことから,以下のような地域での教材開発ができるだろう。もちろん,その地の副読本ではすでに取り上げてあるかもしれないが。
その1つは,「鯖街道」である。若狭湾のサバを京へと運んだ,若狭街道である。小浜と京都を結ぶ道で,小浜で一塩入れたサバは,京都でちょうどよい塩梅になって親しまれた経緯がある。逆に,小浜には京文化が残ると言われている。日本文化遺産にも認定されているところである。「なぜ,小浜に京都に似た仏像や寺院,祭りがあるのだろうか」という発問はいかがだろうか。
もう1つは,駿州往還や中道往還を使った,山梨の煮貝やマグロの輸送である。なぜ,海に面していない山梨県でアワビやマグロなのかという疑問点が当然出てくるだろう。何しろ,山梨県は寿司屋の数が日本一,マグロの購入金額・数量とも全国2位ときている。上記の京都と同じパターンである。つまり,駿河湾でとれたアワビを加工(醤油付け)し,馬の背に乗せて甲州へと運んだのである。マグロも同様に,生魚の状態で運ばれたらしい。富士山麓で,寒冷な道筋でもあったと考えられる。これは,葛飾北斎「富嶽三十六景」の「身延川裏不二」にも登場している。もっとも,こちらは身延山久遠寺への参詣シーンではあるらしいのだが。
「魚尻線」という用語がある。これは,海から内陸へ魚を運搬できる限界点を結んだ線のことだ。甲府は,ちょうどこの限界点に当たっていた。この用語だけでも,教材開発が進みそうな気配がしてくる。
このように,似たようなシーンを見つけ出すのが,教材開発の醍醐味ではなかろうか。そのためにも,望遠鏡(遠くを見る力)と顕微鏡(見えないものを見るようにする力)の2つは必需品である。(「おわりに」に続く!)
-
 明治図書
明治図書- 書いた本人ですが、初任研を担当していて、配本したいと思っていますので、ぜひお願い致します。2024/4/6ムラコウ
- 実践的で使いやすい。2018/8/27アツシ














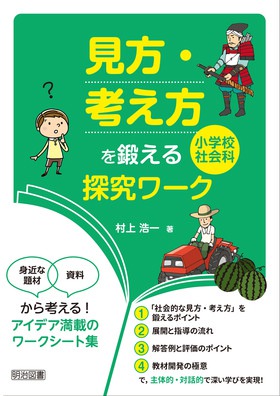
 PDF
PDF
