- はじめに
- 1章 生徒指導とは何かを考えよう
- 生徒指導の意義を学ぼう
- 生徒指導の基本は「納得」
- 生徒指導の目指すゴールとは
- 生徒指導を始める前に心得ておくこと
- 生徒指導の基本はまずは予防から
- 生徒指導の出発点は関係性をつくること
- 子どもに考えさせ、選択させる指導を
- 生徒指導は「連携」して取り組む
- 「報・連・相」を基本としよう
- 負の視点で子どもを見ないことが出発
- 押し続ける指導をしない
- 10年後を見据える指導をする
- 子どもの姿の裏側を見る
- 授業も生徒指導の場であることを忘れない
- 自分の心の状態も意識する
- 2章 生徒指導の学び方を知ろう
- 生徒指導の歴史的背景を学ぼう
- 一人でがんばりすぎない方法を学ぼう
- 生徒指導の土台の対人関係を学ぼう
- 生徒指導を受けてきた自分自身を振り返ろう
- 教師の目、子どもの目をもとう
- 読書を生徒指導に生かそう
- 自分のキャラクターを考えよう
- 逃げずに立ち向かおう
- 検証し、省察しよう
- 指導のうまい先生の理由を考えよう
- 指導の現場を見せてもらおう
- チームでの生徒指導を学ぼう
- 真似してやってみよう
- 子どもと感覚でつながる工夫を
- つながりを求めて一緒に考えるスタンスを
- 記憶するのではなく、記録を取ろう
- 家庭訪問での学び方
- 個に応じた指導を考えよう
- 言葉の使い方を学ぼう
- 自分の家族から学ぼう
- 3章 予防的生徒指導を大切にしよう
- 予防的生徒指導の重要性
- 集団づくりから生徒指導を考えよう
- 日頃からルールを意識させよう
- 笑顔や笑いを取り入れよう
- 子ども同士の関係をつくろう
- 教師と子どもの関係をつくろう
- 女子のグループ化を大切にする
- I(愛)メッセージで伝える
- YOUメッセージでほめる
- 子どもとの距離を考えて指導しよう
- 子ども達を認める場を常に考え、工夫する
- 指導の時間に気をつける
- 情報モラルの指導を丁寧に
- バランスをもって指導をする
- 怒鳴る教師にならないための工夫を
- 指導の方針を大切にする
- よい時にも保護者に連絡を
- 積極的に関わる工夫をしよう
- 家庭との連絡の取り方で気をつけること
- 二者懇談の工夫をする
- トラブルを防ぐためのちょっとした工夫
- 4章 対応型生徒指導について考えよう
- 事故や事件が起きた時の初期対応
- 情報集め=事実の確認が指導の8割
- 冷静な判断で指導をする
- 話を聞く姿勢をもつ
- ケンカの対応
- 問題行動時の連絡の仕方は進行形で
- 指導の場を意識的に変えるようにする
- 包み込み指導の重要性
- 子どもの背景を考えて指導する
- 指導後の連絡と記録の仕方
- 三者懇談のコツ
- 保護者の話の聞き方
- フォローの意識を大切にする
- ゆずらず、ぶれない
- ピンチはチャンスの心構え
- ・学びを深めるために
- おわりに
- 引用および参考文献
はじめに
忘れられない言葉があります。
それは、生徒指導において素晴らしい実践を残された故家本芳郎先生が、
「指導という言葉が汚れてきている」(『教育力をみがく』寺子屋新書)
と書かれた一文です。
生徒指導のイメージは
・こわもて
・なめられない
・しめる
・強気
といった言葉がおどります。さらに、あってはいけないことですが、過去には時に手を出すことが是認されているような状況が見られることもありました。
しかし、指導とは、家本先生いわく、
「道をちょっと指で示す」
ことであり、「強気でしめる」ことではありません。
そこで、本書は、
・どんな立場の先生でもできる生徒指導
・特に若い先生や女性の先生を意識した生徒指導
・小学生から中学生まで生かせる生徒指導
を目指して、「指導」とは何かについてゼロから見つめ直すために、小・中学校の若い先生にお願いをして執筆していただきました。
とりわけ、本書のよさは、
予防的生徒指導
について詳しく述べた点です。起きてしまった後の対応だけではなく、起きる前に予防をしたり、トラブルが起きてしまっても、よりよい解決ができるようにしたりする指導の在り方を提案しようと若い先生と話し合い、進めてきました。
多くの先生のお役に立つことができれば幸いです。
執筆者代表 /長瀬 拓也
-
 明治図書
明治図書- 生徒指導について、もう一度考える機会となった。2015/6/1940代・中学校教員














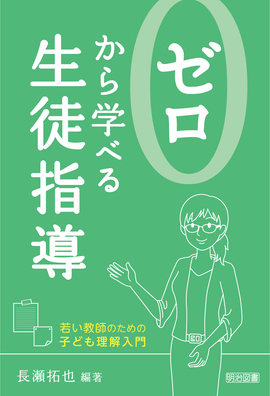
 PDF
PDF EPUB
EPUB

