- はじめに
- 序章 個別最適な学びで見えた子どもたちの可能性
- 1章 個別最適×複線×探究から考える授業デザイン
- ―ロイロノート活用のポイント
- 1 個別最適な学びが描くものとは
- 2 個別最適な学びとICT
- 3 複線型の授業とは?
- ―複線型とロイロノートの相性
- 4 探究的な学びの過程
- ―探究的な学びとロイロノートの相性
- COLUMN1 生徒主体の中学野球部の運営を目指して
- 2章 個別最適な学び×ロイロノート 複線型の授業デザイン
- 1 2年国語 数値で仮説を立証する
- ―生徒の感性を生かした学び―
- 2 1年数学 生徒一人一人に最適化された学びを目指して
- ―3本柱による「個別最適×複線型」の授業実践―
- 3 2年英語 ポートフォリオ学習でそれぞれのペースで学習を!
- ―自由進度学習で個別最適化―
- 4 1年理科 “選ぶ理科”で自律型学習者を目指す
- ―授業内に複数の「学びのコース」がある授業―
- 5 2年社会 どうする?!家康(の評判)
- ―織田・豊臣と江戸幕府の取組を比較・検討を通して,思考力を高める―
- 6 全学年総合 “好き”から始まる探究活動
- ―自分を起点にした「やさしい」プロジェクトたち―
- COLUMN2 Simple is Best
- 3章 個別最適な学び×ロイロノート 探究的な授業デザイン
- 1 2年国語 『壁に残された伝言』を読んでピースミニレポートを書こう
- ―平和を伝える表現の工夫とは?―
- 2 1・3年数学 文字式を活用する良さを自分の言葉で表現しよう(1年)パラボラアンテナの教科横断的なレポートを作ろう(3年)
- 3 1年英語 環境問題について考えてマニフェストを作ろう
- ―思考と分析を繰り返し,自分の考えをまとめる―
- 4 2年理科 モーターはなぜ回り続けるのか
- ―見えないものを可視化しつつ,立体的に観察して考える―
- 5 2年社会 身近な地域を対象とした探究的なプロジェクト学習
- ―フィールドワークとテクノロジーで感性と理性をつなぐ―
- 6 1年教科横断 ストーリーのある素材を用いた学び
- ―複数教科にまたがる学び―
- COLUMN3 ロイロカードを活用して古典の場面をグラフィックレコーディング!
- 4章 悩みを抱えるあなたへ 個別最適な学びを実現するために
- 1 仲間をつくる―学び続けるコミュニティに出会うには?
- 2 仲間をつくる―学校内にどう広げる?
- 3 個別最適と学習目標との整合性は?
- 4 保護者や同僚の理解を得るにはどうしたらいい?
- COLUMN4 共有ノートで協働制作
- おわりに
はじめに
VUCA※と呼ばれる現代,大人でさえ生きていくにはどんな力が必要か,どのような学びが効果的かに迷う中ではありますが,子どもたちは日々学び続け,未来に向けて進んでいます。教育の世界でも「GIGAスクール」「学びのDX化」「令和の日本型学校教育」など次々と新しい用語が生まれ,現場にいる先生方も情報の渦の中でもがき,必死に前に進んでいるのではないかと思います。本書は,2024年に発刊された『個別最適な学び×ロイロノート 複線型の学びを生み出す授業デザイン 小学校編』の中学校編として,そんな中でも前を向き続け,ワクワクした気持ちを爆発させながらさまざまな実践を生み出してきた,素敵な著者の皆様のエッセンスを紹介しています。
序章では,本書のキーワードである「個別最適な学び」によって広がった子どもたちの可能性,大人が驚くような成長を遂げた生徒たちの姿を紹介します。1章では,現代社会を分析し,何が必要なのかを丁寧に提示している答申を参考にしながら,「個別最適化とは何か」を紐解いていきます。2章,3章はいよいよ本題。2章は「学びの複線化」をテーマに,教室内で複数の学び方や学びの成果が生まれる実践の紹介です。3章は「探究的な学び」をテーマに,教科書の内容にとどまらない,生徒が自走して学び続ける姿が育まれる実践の紹介です。そして,4章ではそれでも不安が残る方のために,仲間を集めたり学校で想いを共有したり,一歩踏みだす勇気を得られるような情報をお伝えしています。
中学校の教育の書籍では,教科ごとの指導法に分かれることも多いと思いますが,本書ではあえて複数の教科を紹介させていただきました。自教科にはない視点を知ることで,新しいアイデアや自教科に応用できる気づきに出会えると思います。ぜひご自身の教科だけでなく,さまざまな教科の実践を読んでいただければと思います。
/奥津 憲人
※Volatility(変動性),Uncertainty(不確実性),Complexity(複雑性),Ambiguity(曖昧性)
-
 明治図書
明治図書- 実際にロイロノートを使って授業を行なってみたくなりました。2025/8/2930代・中学校教員














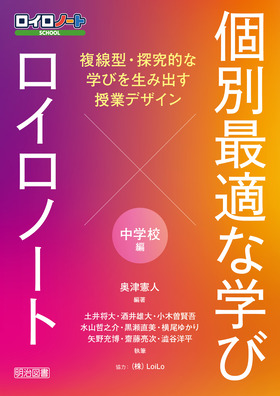
 PDF
PDF

