- 『形式的な評価のために』復刻版に寄せて
- 1章 教育評価を考え直す
- 1 新しい評価研究への転換
- 2 形成的評価の理念と志向
- 3 行きすぎた評価実践例
- 4 実践的な評価研究の手順とポイント
- 5 「開・示・悟・入」からの再検討
- 6 授業に期待されるもの
- 7 基盤としての三条件
- 2章 新しい評価観と学習指導
- 1 新しい評価観への転換
- 2 教育実践に何がもたらされるか
- 3 学ぶ側の論理への「呼びかけ」
- 3章 評価研究の実践的展開
- 1 評価研究の盛り上がり
- 2 授業改善への評価研究
- 3 上構型の研究と下構型の研究
- 4章 評価を教育化するために
- 1 評価は科学的合理的であればよいか
- 2 向上目標も体験目標も
- 3 すべてを評価できるか
- 4 目標と計画の上に躍動する実践を
- 5 多様な評価活動を
- 5章 形成的評価の考え方と課題
- 1 形成的評価の基本的な考え方
- 2 当面する課題と今後の発展方向
- 3 形成的評価の目的の再確認
- 6章 形成的評価と学習意欲
- 1 評価的な活動と効力感
- 2 記録やデータから形成的な評価へ
- 3 形成的評価の手だてと学習意欲
- 7章「関心・態度」の評価
- 1 客観的で厳密な評価ということについて
- 2 「関心・態度」はなぜ大切なのか
- 3 「関心・態度」の目標をどう明確化するか
- 4 目標分析の枠組みをどう考えるか
- 5 実態の把握と評価基準の設定
- 8章 到達度テストとその生かし方
- 1 到達度テストとは何か
- 2 どう活用するか
- 3 形成的なはたらきを
- 4 単元の形成的テスト
- 5 目標の分析・明確化
- 6 テスト問題の様式
- 7 高次の能力を測る
- 8 高次能力のテスト問題
- 9 ペーパーテストの限界を乗り越える試み
- 10 「正解」の設定法をめぐって
- 11 テスト結果から何を検討するか
- 12 階層分析
- 9章 「色」と「空」と形成的評価と ――結語に代えて
- あとがき
『形成的な評価のために』復刻版に寄せて
PDCAサイクルの意義の再確認を
教育活動を計画的かつ着実な形でやっていくためには、P(計画)・D(実施)・C(評価)・A(補充/深化)といったサイクルをきちんと踏む形で取り組まなければならない。こうしたPDCAサイクルは、また、O(目標)に向けての意識抜きでは機能しない。つまり、これこれの教育目標(O)を実現することを目指して、このような計画(P)を立て、こう実践(D)し、その目標(O)がどう実現してきているのかを評価(C)して、その結果を補充や深化といった次の段階の取り組み(A)に生かしていく、ということでなくては、計画的かつ着実な教育活動にはならないのである。
最近こうした考え方が、中央教育審議会の報告等をはじめ各種の公的文書にしばしば現れるが、このことはまさに、一九八六年に本書で述べた「形成的な評価」の考え方そのものと言ってよいであろう。
しかしながら、日本の教育界には、こうしたPDCAサイクルとか形成的な評価といった発想で教育活動に取り組むということが、必ずしも十分に浸透しているわけではない。目標を明確化し、その実現状況をきちんと評価しながら必要な手を打っていく、といった合理主義的な発想は、日本の教育界になかなかなじまない面があるのだ。
日本の教育界には、一種の精神主義が伝統的に存在している。教師の側にも学習者の側にも、その時その場を「一所懸命」やっていくことが無条件に求められている。「純粋な」精神的態度が重視されるのである。したがって、今ここで取り組んでいくことによって結局何が実現すればよいのか、という目標がはっきりせず、それがどの程度実現しているのかも意識しないまま、その場その場で全力投球することばかりが求められることになる。これでは、長い年月にわたってきちんとした教育成果を積み上げていくことは困難、と言わざるを得ない。
もう一つ、日本の教育界には、見かけ上の好ましさのみを追究する、印象主義とでも言うべき悪弊が伝統的に存在している。例えば「ゆとり教育」の時期には、文部省の教科調査官も大学に籍を置く教育学者も、「子どもたちの目がキラキラ」とか「教室の皆がイキイキ」といった言葉で教育を語っていた。我々は、「目がキラキラしていても、それでちゃんとわかってるの?」「皆がイキイキとしていても、それでちゃんとできるようになってるの?」と批判してきたものである。また、「教師が何も教えないで、子どもたちが自分たちだけで授業を作っていくのが最高の授業のあり方」であると説く人気教育学者がいて、それを無批判的に信じた少なからぬ教師が、実際の「子どもが作る授業」を見に、「実践有名校」詣でをする、といった時期もあった。私自身も何度かそうした学校を見に行ったが、「仕組まれた劇」としての授業パフォーマンスを見せられただけで、その学校の子どもたちに着実に学力が形成されているとはお世辞にも言えない、という感想をもっている。こうした印象主義も、PDCAサイクルとか形成的な評価といった発想とは対照的な地点にあるものと言っていい。
それだけではない。目標をはっきりさせて、PDCAサイクルで取り組まないと、いつの間にかマンネリに陥ってしまうことにもなる。決められたことを決められたようにこなしていくだけで満足してしまうことになってしまうのである。学校の教師の場合で言うなら、朝何時に学校に行って夕方何時まで勤務し、年間の授業時数をきちんとこなし、教科書をきちんと終わりまで上げる、といったことだけでもう十分という感じになってしまうのである。しかし、具体的な「願い」も「ねらい」もないまま、それを実現するための意図的計画的な取り組みの姿勢も欠いたまま、さらには学習者の実際の学びや育ちの成果に何のこだわりももたないまま、ということでは、まさに無責任なマンネリ教育と言うしかないであろう。
「一所懸命であればよしとする精神主義」にも、「見た目だけの印象主義」にも、さらには「無責任なマンネリ」にも陥らないようにするためには、本書で述べているような評価意識を常にもつことが不可欠となるであろう。つまり、「教育の成果」へのこだわりである。一定の目標意識と、それを実現するための計画性と、そして目標の実現状況を適時適切にとらえて次のステップに生かしていく姿勢である。私自身、一九八六年の時点で本書に述べたところを再読しながら、現時点においてもなお、教師の方々をはじめ、教育に関心をもつすべての人に、「成果に責任をもつ教育のあり方」について再認識、再確認していただきたい、と強く思ったところである。
本書の復刻が、日本の教育界にとって、こうした本来の着実な教育を実現していくうえで新たな刺激となってくれれば、と心から祈っている。
なお、形成的評価の考え方を中心としたベンジャミン・ブルームの理論が、日本の教育研究の中でどのように受け止められ、現実の授業実践の中でどう生かされてきたかについては、私の最近のレビュー「ブルーム理論の日本における実践化」(拙著『人間教育のために』金子書房、二〇一六、一四一〜一六九頁)がある。ご参照いただければ幸いである。
二〇一六年九月 /梶田 叡一






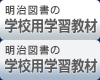


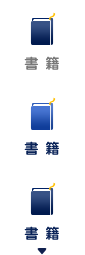
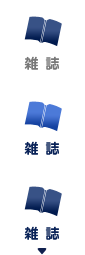




 ▲クリックで拡大表示できます
▲クリックで拡大表示できます
 PDF
PDF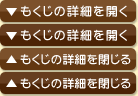


若い先生方にも、「評価」について学ぶ際に、手にとっていただきたい。