- �͂��߂�
- ���́@�w�Z�S�̂Łu�q�ǂ���́v�Ɏ��g�ޓy������邽�߂ɍl����������
- 01�@�q�ǂ��ւ̎v�����m���߂�\�����������߂�
- 02�@�q�ǂ��ւ̎v�����`�ɂ���\���l�����ۂ��鋳��ے��̑n��
- 03�@�q�ǂ��ւ̎v�����ɂ���\�������ʂ���
- ��P�́@�u���w���K�v�Ɗw�т��q�ǂ��Ɉς˂�w�Z�Â���
- 01�@�w�т̎哱�����q�ǂ��Ɉς˂�\���w���K�̎�g��ʂ���
- 02�@�����e�[�}�u�����̊w�т�����q�ǂ��v
- 03�@���H�@�@�P�N�@�����ȁu���ӂ����ā@�����Ƃ��̂��������т����낤�I�v
- 04�@���H�A�@�R�N�@�Z���ȁu�����@���̕\������d�g�ׁ݂A�������L���悤�v
- 05�@���H�B�@�U�N�@����ȁu�ǂނ�����ށ@�����a���́w�C�̖��x�v
- 06�@�q�ǂ��͎��w���K���ǂ����Ă���̂�
- 07�@�w�т̎哱�������ׂĂ̋��犈���Ɍ��o��
- ��Q�́@�u�P�������R�i�x�w�K�v�Ɗw�т��������ɂ���w�Z�Â���
- Part1�@���Ɍ��O�؎s�����u�����w�Z
- 01�@�q�ǂ���̂̊w�т�������ƂÂ���
- 02�@�l�o�r�̋�̗�@�@�P�N�@�Z���ȁu�������Â���v
- 03�@�l�o�r�̋�̗�A�@�R�N�@�Z���ȁu�~�Ƌ��v
- 04�@�l�o�r�̋�̗�B�@�T�N�@�Љ�ȁE���y�ȁu�����Ԃ�����H�Ɓv�u�\���L���ɉ��t���悤�v
- 05�@�l�o�r��ʂ��Ďq�ǂ������͂ǂ��ω�������
- 06�@������������u�Ί炠�ӂ��y�����w�Z�v
- Part2�@��t�������s�����c���w�Z
- 01�@�i��Ŋw�тɌ������q�ǂ�����Ă����
- 02�@���H�@�@�}��H��ȁu���낢��Ȃ�ׂāv���R�n�슈��
- 03�@���H�A�@���ȁu���̂ӂ����v�ۑ�ݒ�w�K�E�P�����ۑ�I���w�K
- 04�@���H�B�@�Z���ȁu�v�����g�w�K�v���w�N���ۑ�I���w�K�E���R�i�x�w�K
- 05�@���ꂩ��̊w�Z����̎��_
- ��R�́@�u�����v�u�Z���v�̉��v�Ǝq�ǂ������t����w�Z�Â���
- 01�@�q�ǂ������t����w�Z������
- 02�@�V�����w�Z�����钧��
- 03�@�����I�Ȋw�K�̎��Ԃ����ɂ���܂ł̊w�Z�݂̍����₤
- 04�@���H�@�P�������R�i�x�w�K�i�Љ�ȁE���ȁj
- 05�@�w�Z�����������
- ��S�́@�u�q�ǂ������v�ɂ������Ɖ��P�Ɗw�Z�Â���
- 01�@�w�ё�����q�ǂ��̈琬��ڎw����
- 02�@���H�@�@��w�N�@�����ȁu�w�Z����v�u������v
- 03�@���H�A�@�T�N���@���ȁu���̂̂Ƃ����v
- 04�@�q�ǂ��̕ϗe�@�@�q�ǂ��Ƌ��t�����Ɋw�сA���
- 05�@�q�ǂ��̕ϗe�A�@�U�N�Ԃ̎q�ǂ��̈炿
- 06�@�w�Z�o�c�ɂ�����w�Z�����̈ʒu�t��
- 07�@�q�ǂ������Ɓu���ɖڎw���w�Z�v
- ������
- �Q�l�����ꗗ
- ���M�҈ꗗ
�͂��߂�
�q�ǂ������t���K���ɂȂ�w�Z������
�u�ڂ��̓o�J�Ȃ�ł��v
�@���ƒ��A�L���ɏo�Ă����`����Ɂu�������Ă�́v�Ɛq�˂��ۂɕԂ��Ă������t�ł��B��k�Ƃ����l�q�ł͂Ȃ��^��ł��������܂����B����܂ŁA�`������������Ȃӂ��Ɏv���Ă���Ɗ��������Ƃ͂Ȃ������̂ŋ����܂����B�����āA�q�ǂ����������u�o�J���v�Ɩ{�C�Ŏv���A�������킴��Ȃ��w�Z�ɂ��Ă���̂�����Z�����i���Ɣ��Ȃ��܂����B�R�`���̓V���s���V���������w�Z�ɒ��C�������̂��Ƃł��B
�@�����V���s���������w�Z�Ŋw���S�C�����Ă������A���䏇��Z���搶�́u����͎q�ǂ����K���ɂ���w�͂��v�Ƃ���������Ă��܂����B�w���厖�Ƃ��ēV���s����ψ���ł����b�ɂȂ��Ă��鎞�A���䏇�ꋳ�璷�́u�q�ǂ��̗͂��L�т�̂Ȃ�A�����Ȃ����ł�����Ă����v�Ƃ���������Ă��܂����i����搶�͓���l���ł��j�B�������������Ă����������ɂ�������炸�A�Z���Ƃ��ċΖ�����̂��Ō�̊w�Z�ɂȂ肻���Ȓi�K�ŁA�܂��q�ǂ��ɔ߂����v���������Ă����Ȃ��Ȃ�܂����B�������A���N�̎��Ԃ͎c���Ă��܂����B���_��A���āA�q�ǂ����K���iWell-being�j�ɂȂ�w�Z�����낤�ƌ��߂܂����B���̂��߂ɂ͎��Ɖ��P�ɐ��ʂ�����g�܂Ȃ���Ȃ�܂���B�w�Z����̒��͎��Ƃ�����ł��B�]���̋��t�哱�̎��Ƃł͂Ȃ��A�w�ю�ł���q�ǂ���̂̎��Ƃ������������ƍl���܂����B�����v���������Ƃ�����K�v�����肻���ł������A�ꏏ�Ɏd��������̂́A���J�ɐ��������đ��k���J��Ԃ��Δ[�����Ă���鋳�E���ł����B�q�ǂ������̊w�Z�����̗l�q���ς���Ă���A�o��������Ď�̓I�ɓ����Ă���������ł����i���̂�����̂��Ƃ͏��͂ʼn��߂ďq�ׂ����Ă��������܂��j�B
�w�т̎��R�x���グ��
�@�q�ǂ��͈�l��l���L�\�Ȋw�ю�ł��B�Ԃ���w�ԗl�q�����Ă���Ƃ悭�킩��܂��B���t�ɂ��Ă��A�������莎�����莸�s���J��Ԃ��Ȃ���A�������������Ď����̂��̂ɂ��Ă����܂��B����̑�l�ɋ����Ă��������m�F������͂��܂����A�������w�т����E�w�ׂ�Ǝv�������Ƃ������̈ӎv�Ŋw��ł����܂��B����͏��w���ł������ł��B�q�ǂ��͂���܂ŁA�����̗͂ł�������̂��Ƃ��w��ł��Ă��܂��B�ɂ�������炸�A�u�����̓o�J���v�Ɩ{�C�Ŏv���Ă��܂��̂́A�Ȃ��ł��傤���B�w�Z���x�A�w�������̎��ƂƂ̐܂荇���������A�ӗ~�������Ď����̗͂��ł��Ȃ����߁A�w���҂�ی�ҁA�ꍇ�ɂ���Ă͒��Ԃ�����ے�I�Ȃ��Ƃ�����ꑱ���Ă��邤���ɁA����Ȃӂ��Ɏv���悤�ɂȂ�i�v�����܂����j�̂ł��B�q�ǂ��͗L�\�Ȋw�ю�ł����A�݂�Ȃ������悤�Ɋw�ׂ�킯�ł͂���܂���i�����悤�Ɋw�ׂ�K�v���Ȃ��ł��傤���j�B�����E�S�̕����A�w�ԃy�[�X�A�K�v�Ȏ��ԁA���ӂȊw�ѕ��Ȃǂɂ͈�l��l�Ⴂ������܂��B
�@�����ŁA�q�ǂ���M�����A�w�т̎��R�x�����߂����Ƃ�������邱�Ƃɂ��܂����B30�l�ȏ�̎q�ǂ������ɑ��āA��l�̋��t���P�́A�����Ă�����ނ̊w�ѕ��������Ƃ������J��Ԃ��Ă��ẮA����ɍ���Ȃ��q�ǂ������������ł��Ȃ��͓̂��R�ł��B�݂�ȂƓ����悤�Ɋw�ׂȂ������ŁA�u���Ƃ͂܂�Ȃ����̂��v�u�����̓o�J���v�u���߂��v�Ǝv�����ƂɂȂ�܂��B���ۂ͋�������g���Ă��鋳�ނ��A���̎q�ɂ͍����Ă��Ȃ������Ȃ̂ł��B
�@�������A���˂Ɂu���ׂĂ����R�ł��v�u�ǂ����D���Ɋw��ł��������v�Ɠ˂������Ă��w�т̎������シ��Ƃ͍l���ɂ����A�������Ȣf���Ă��܂��q�ǂ��������Ȃ肻���ł��B���̂��߁A�q�ǂ��⋳�E���ɑ��k�����s���Ȃ���A�w�т̎��R�x�ɍ��킹�ĂR�̎��ƃX�^�C����i�K�I�ɓ������܂����B�����ꂽ���Ɂu���w�E���K�v�u�}�C�v�����w�K�i�P�������R�i�x�w�K�j�v�u�t���[�X�^�C���v���W�F�N�g�i�l�����j�v�ł��i�ڍׂ͏��͂Łj�B
�@���������w�тɂ��A�u���ԂƋ��t�őn����Ɓv�i������A��Ď��Ɓj�̎����ς���Ă���i���ƒ��ɁA�L���ɏo�Ă��܂��q�ǂ��͌���j�ƍl���܂����B���R�x�������w�т��o�����邱�ƂŁA���t���狳���Ă��炤���ƂɎq�ǂ��͉ߓx�Ȉˑ������Ȃ��Ȃ�܂��B�����炵���w�Ԃ��ƂɎ艞���������Ă����܂��B�����̊w�т��[������A����̒��Ԃ̍l���������Ă݂����A�ꏏ�ɘb�������Ă݂����Ǝv���悤�ɂȂ�܂��B���Ԃ⋳�t�Ƃ̊w�т��������狁�߂邩�炱���A��l�Ŋw�Ԃ��ƂƂ̈Ⴂ���������W�c�Ŋw�Ԃ��ƂɈӋ`�����o���A���ʂƂ��ďW�c�̊w�т̎������܂��Ă����܂��B�u�w�ʍœK�Ȋw�сx�Ɓw�����I�Ȋw�сx�̈�̓I�ȏ[���v�ɂ���āu��̓I�E�Θb�I�Ő[���w�сv�̋�����}���܂��B
����܂ł̊w�Z�ւ̊�@��
�@�����w�Z�̋�����ސE���Ă���A�l�X�Ȏ����̂�w�Z����ꏏ�Ɋw�Ԃ��������������Ă��܂��B���ʂ��Ă���̂́u����܂ł̊w�Z�v�ւ̊�@���������Ă��邱�Ƃł��B�q�ǂ��Ɋւ��ẮA�����Ȋw�Ȃ̒����ŔN30���ȏ�o�Z�����u�s�o�Z�v�Ƃ��ꂽ�����w���́A�Q�O�Q�R�N�x�͉ߋ��ő���34���U�S�W�Q�l�ƂȂ��Ă��܂��B�O�N�x���S���V�S�R�S�l�����A������11�N�A���łQ�O�Q�O�N�x�ȍ~�ɖ�15���l�����Ă��܂��B����A�����Ɋւ��ẮA�����Ȋw�Ȃ̒����ɂ��ƁA�Q�O�Q�R�N�x�Ɏ��{���������̗p�����Ō������w�Z�̋����̗̍p�{���́A�O�N�x���0.1�|�C���g����2.2�{�A���w�Z��0.3�|�C���g����4.0�{�ŁA��������P�X�V�X�N�x�̒����J�n�ȗ��A�ߋ��Œ���X�V���Ă��܂��B�q�ǂ��������w�Z���牓�������Ă��邱�ƂƋ����̊�]�҂������������Ă��邱�Ƃ������ɐi�s���Ă��܂��B�����̍��{�I�Ȍ����͓������ƍl�����Ă��܂��B�[�I�Ɍ����A�����Ŋw�Ԏq�ǂ��������Ŏd���������҂��u����܂ł̊w�Z�v�ɖ��͂������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł��B
�@�����������������w�Z�́A�������������Ƃ��Ŕj�������ƍl���Ă��܂��B�]�O�̂悤�ɁA�u�����̎q�ǂ�����Ă�v�Ƃ����w�Z����ڕW���f�����t���O�ʂɗ����Ĉ���������́A�q�ǂ���l��l���ǂ��w�Ԃ̂��ɖڂ������A���̈ӗ~��w�ѕ����x���邱�ƂŌ��ʓI�Ɋw�т̎������߂Ă������ƍl���Ă��܂��B�q�ǂ��ɂƂ��ċ��S�n���悭���͓I�Ȋw�Z�Â���ɗ��ł��鎩���̂�w�Z�ł́A���f�����邽�тɎ��Ƃ��ς��A�q�ǂ������̂��炵�̗l�q���ϗe���Ă��܂��B���E�����A�q�ǂ��ɖ{�C�ŊS���o��������Ď��g��ł��邱�Ƃ͎q�ǂ��ɓ`���܂��B�w�Z���Ȃ��Ȃ��ʔ����A���Ԃƈꏏ�Ɋw�Ԃ̂͊y�����A�搶���͐M���ł����l���ƁA���E���̐S�ӋC�ɔ������܂��B�q�ǂ����ς��A���E���̎w���͂��K�Ȃ��̂ƂȂ�A�ی�҂�n��̕��X�̊w�Z�ւ̐M���x�����܂�܂��B���������D�z�Ŋw�Z�S�̂����R�ɂ܂Ƃ܂萨�����o�Ă��܂��B
�@�{���̂P�͂���S�͂ł́A���������������Ă���w�Z�̒�����T�Z�Ɏ��H���Љ�Ă��������܂��B�e�n��Ō����̐��ʂ��L�����J���Ă���w�Z����ł��B�P���Ŋw�Ԃ��Ƃւ̈ӎ������߁A�q�ǂ�����̓I�Ɋw�Ԃ��߂̋��t�̖������������Ă��邱�Ƃ����ʂ��Ă��܂��B�P���Ԃ̎��Ƃ̎����グ�邱�Ƃ͑�ł����A���t�̎w���Ɣ���Ɏq�ǂ����������Ă��邾���ł́A�u��̓I�Ɂv�w�Ԃ��Ƃɂ͂Ȃ�܂���B���t�̌Ăт����Řb���������d�g�܂�邾���ł́A�u�Θb�v�ւ̕K�v���͍��܂炸�[�����������܂���B���t�̓s���Ŏ��Ƃ��P���Ԃ�����Ă�����w�K�������א�ɂȂ��Ă����肵�ẮA�u�[���w�сv�̎����͓���Ȃ�܂��B������̊w�Z�ł��A���t���O�ʂɏo�Ďw�������ʁA�q�ǂ��������̊S�E�ӗ~�ɉ����Ċw�т�i�߂��ʁA����̕]���Ŋw�т��O���C�������ʂȂǂ��Ӑ}�I�E�v��I�ɑg�ݍ��킹�A�q�ǂ��ɂƂ��ĈӖ��̂���܂Ƃ܂�Ƃ��Ď��Ƃ��A������悤�P�����\�����Ă��܂��B
�@����ŁA�ڂ̑O�̎q�ǂ��̎��Ԃ⋳�E���̏͊w�Z���ƂɈقȂ�܂��B���������āA���Ɖ��P�̒��Ƃ������ɂ͈Ⴂ���o�Ă��܂��B�Ƃ�����ƁA�\�ʓI�Ȏ��ƃX�^�C�������ڂ��ꂪ���ł����A��ɂ��ꂪ����̂ł͂Ȃ��A���ʓI�Ɏ��g�܂�Ă�����̂ł��B
�@�e�w�Z�ɂ́A��g�S�̂̊T�v�A��̓I�Ȏ�g�̗�A�q�ǂ��̕ϗe�A�Z�����̊w�Z�̐擱������̋��E���ւ̓��������A�Ƃ��������_�Ŏ��H���Љ�Ă��������܂��B
��P�́@�R�`�����R�������菬�w�Z�c�P���v��̒��ɁA�l�X�Ȍ`�ԁE�Ӗ������́u���w���K�v���Ӑ}�I�Ɏ�����Ȃ���w�т��[�������Ă��܂��B
��Q�͇@�@���Ɍ��O�؎s�����u�����w�Z�c�w�Z�S�̂ŔN�Ԃ̋���ے��Ɂu�P�������R�i�x�w�K�v�����ʓI�Ɏ�����Ċw�K�ւ̈ӗ~�����߂Ă��܂��B
��Q�͇A�@��t�������s�����c���w�Z�c�q�ǂ������̎��Ԃɍ��킹�āA�u�P�������R�i�x�w�K�v��u�ۑ�I���w�K�v���_��Ɏ�����Ċw�K���ʂ����߂Ă��܂��B
��R�́@�{�錧�������������w�Z�c�J�Z�Ɠ����ɑ����I�Ȋw�K�̎��Ԃ̉��ς��厲�ɐV�����w�Z�Â���ɐ��k�Ƌ��Ɏ��g�݁A�w�Z�������ω����Ă��܂��B
��S�́@�R�`���V���s���V���������w�Z�c�u�q�ǂ���̂̎��Ɓv�Ɍp�����Ď��g�ނ��ƂŁA�q�ǂ��������u���S�n�̂悢�w�Z�v�����낤�Ƃ��Ă��܂��B
�@�e�w�Z�̋��E���̔M���v�����g�ւ̊o�傪�A�u����܂ł̊w�Z�v�Ɋ�@��������Ă���ǎ҂̕��X�ɓ`���A�q�ǂ������ɂƂ��ċ��S�n���悭�w�эb��̂���A�q�ǂ������E�����K���ɂȂ�w�Z�Â���̂��߂̐V���Ȉ���ݏo���m���Ȃ��������ƂȂ邱�Ƃ�����Ă��܂��B
�@�@2025�N�T���@�@�@�Ғ��ҁ@�^��J�@�֎i
-
 �����}��
�����}��- ���H��������ƒm�肽������2025/8/2240��E���w�Z����














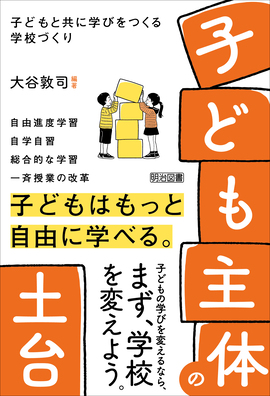
 PDF
PDF

