- イントロダクション
- 短く、印象的な講話で、生徒の心を整えよう
- 4 April
- 出会い 偶然には変化を起こす力がある
- 目標 目標を可視化する
- 計画、見通し 見通しは、やってから立ててもいい
- 発信、前向きさ 好きなことを話すと、前向きになれる
- 立場と自覚 やりたいこととやるべきこと
- 強み、自信 当たり前も自分の強み
- 決断、不安の解消 決断して、他のことは忘れる
- 人間関係、利他 利他の心をもつ
- 価値観、他者理解 相手を知るとは、その人の価値観を知ること
- 部活動、努力 陰の努力
- 5 May
- GW、休むこと 休むことが成長につながる
- 休み明け、気持ちの立て直し 背筋を伸ばすと、気持ちが前向きになる
- 仲間とのつながり、協力 同じ方向を向いて、足並みをそろえる
- 礼儀、敬意 見えないお辞儀
- 忍耐、困難 耐えて力をつける
- 給食、健康 嫌いなものから食べてみる
- 体育祭、協力 大事なことは明文化する
- 宿題、テスト勉強 一番大事なことを優先して行う
- 家庭学習 道具のせいにしない
- 行動、勇気 関心をもったらすぐに試してみる
- 利他 「送りバント」の考え方
- 定期テスト、準備 効果的な覚え方
- 6 June
- 友だち よき友は人生のすべて
- 友だち、健康 人を大事にすることは、自分を大事にすること
- 人間性 人間性を磨く
- 目標の共有 同じところを目指す
- 言葉 NGワードを言わない効果
- ものを大切にする心、リサイクル ものを大切にする心が、環境を守る
- 気の緩み、緊張感 あえて自分に厳しくしてみる
- 柔軟性、発想 不足は発想の母
- 時間意識 時間は有限の貴重な財産
- 苦手の克服 少しずつたくさん触れる
- 7 July
- 短所と長所 短所をひっくり返して見てみる
- 弱みと強み 弱みをさらけ出す
- 苦手、失敗 できないことのよさ
- 自己肯定感 自分は価値のある人間だと信じる
- 成長、初心 初心に帰る
- 振り返り 見方を変えて好意的に振り返る
- 夏休みの課題、自由研究 集中して取り組めば、ヒントは向こうからやってくる
- 夏休みの生活習慣 生活習慣を元に戻すのは意外に大変
- 夏休みの過ごし方 夏休みは挑戦のとき
- 掃除 本気で掃除に取り組む
- 夏休み明け 脳を休ませる
- 進路選択 思っているだけで何もしないのは、本気ではないということ
- 9 September
- 新学期、リスタート 古いものを捨てる勇気
- 粘り強さ、根気 粘り強さが成果を生む
- 基本的な生活習慣 あいさつ、掃除、言葉づかい
- 志、将来の目標 志を立てる
- 困難との向き合い方、リセット 逃げることも選択肢の1つ
- 物事を捉える視点 ネーミングで多面的に見る
- 体育祭 結果よりも過程が大事
- 10 October
- 読書 読書は身を助ける
- 約束 約束を守ることの大切さ
- 定期テスト、努力 あり得ないほどの努力
- 恋愛 自分自身を見失わない
- 悩み、見返り 悩みやストレスの原因
- 自信、自己暗示 自分に暗示をかける
- 厳しさ、成長 厳しさが人を成長させる
- 柔軟性、発想力 先入観から逃れる
- 整理整頓 人生の半分は整理整頓
- 防災、避難訓練 捨てていく勇気をもつ
- 進路選択、受験勉強 基礎基本を大事にすることを忘れない
- テスト勉強 インプットとアウトプット
- 11 November
- 友人関係 偏見に気づく
- 人権意識 流言は智者に止まる
- 感謝、幸福 今ここにある幸せに気づく
- 責任、誠実 小さな仕事を誠実にやり遂げる
- 家庭学習 必死に学ぶ経験
- テスト勉強、教え合い 教え合いの効果
- 自重、他者尊重 脚下を見る
- 主体性 一を聞いて十動く
- 学校祭 感動は自分たちの手で生み出す
- 12 December
- 通知表、成績 成功は失敗のもと
- 生徒会 みんなで考えるからよいアイデアが生まれる
- 冬休みの活動 アウトプットを通して学ぶ
- 1年の振り返り よくない思い出をよい思い出に変える
- 1年の締め括り やり抜くことで自信をつける
- 伝統文化 伝統や文化に触れる
- 健康管理、習慣化 楽しいことは習慣化できる
- お年玉、お金の使い方 お年玉はご褒美
- 1 January
- 目標 具体的な行動を目標に
- 入学(就職)試験 神頼み
- 目標 立派な人を目指して行動する
- 時間の使い方、締切感覚 締切を守るコツ
- 当番、係活動 自分の得意を生かせる場は必ずある
- 食育 好きなものばかり食べない
- 進級 物事を新しい視点で見る
- 2 February
- 先輩、後輩 待って認める
- 勉強、学ぶことの意味 勉強する理由
- 日々の努力 今から少しずつ積み上げる
- 友人関係 相手のよいところを積極的に見る
- 努力、定期テスト 努力しないで結果は出ない
- 復習、学習のまとめ 自分で自分を励ます
- 思い出、経験 モノよりコトを大切に
- 健康管理、基本的な生活習慣 基本的な習慣が大事
- 3 March
- 感謝、進級・卒業 1日生きれば1日分の感謝
- 準備 準備万端整える
- 夢 夢をもつことで強い意志が生まれる
- 才能、努力 努力が才能を開花させる
- 愛校心 あるがままを愛する
イントロダクション
短く、印象的な講話で、生徒の心を整えよう
1 エピソードを語る意義
校長先生の講話は、多くの学校で定期的に行われます。生徒にとって校長先生の講話は「見慣れた景色」でしょう。そうなると、徐々に新鮮味も薄くなり、生徒の関心も下がっていきます。
しかし、そんな「見慣れた景色」である校長先生の講話が、生徒たちから、
「今日は校長先生はどんな話をしてくれるのだろう。楽しみだ」
と思われるようになったらどうでしょうか。
生徒は校長先生に親近感を覚え、校長先生の存在をより身近に感じるようになり、ますます校長先生の講話を楽しみにするようになるでしょう。そして、そのことは、校長先生が目指す学校経営や学級担任の学級経営、生徒指導などを支える、大きな力になるに違いありません。
では、校長先生の講話が、生徒たちから心待ちにされるようになるためには、どうすればよいのでしょうか。
その1つの方法が「エピソード」を語ることではないかと思います。
なぜなら、エピソードを語ることには、次のようなよさがあるからです。
1 わかりやすい…具体的なイメージがわきやすく、生徒が講話の内容を理解しやすくなります。
2 興味を引きやすい…内容が理解しやすいため、生徒の興味を引きやすくなります。
3 思いを伝えやすい…生徒が興味をもって聞くので、校長先生の思いを伝えやすくなります。
4 生徒の心に響く…感情移入しやすくなるため、生徒の心に響きやすくなります。
5 記憶に残りやすい…具体的な内容は記憶に残りやすく、校長先生の思いが長く留まります。
このように、エピソードを語ることによって、生徒たちに校長先生の思いのこもった、生きた教えを伝えることができ、しかも長く生徒の心に留めることができるでしょう。
2 エピソードを語る際に意識したいこと
先に述べたように、エピソードを語ることには多くのよさがあります。エピソードそのものに、生徒の心に訴えかける力があるからです。
ですから、エピソードを語るだけでも、校長先生の思いを生徒に伝えることができるでしょう。
しかし、生徒も千差万別です。聞くことが得意な生徒もいれば、不得意な生徒もいます。野球に興味のある生徒もいれば、ピアノの演奏が好きな生徒もいるでしょう。生徒全員が、同じ話に同じように関心をもつとは限りません。
そのような多くの個性の集まった生徒たちに向かって話すのですから、エピソードの内容が、より確かに、より効果的に伝わるようにするためには、少しの工夫が必要になります。
そこで、エピソードを語るうえでのちょっとした技術について、校長先生にとっては釈迦に説法だとは思いますが、いくつかあげてみたいと思います。
校長先生自身の思いを込める
まず、1つ目は「校長先生自身の思いを込める」ということです。
あまりにも当たり前のことですが、「このことを何が何でも生徒にわかってもらいたい」という強い気持ちをもって語ることで、言葉に力が加わり、生徒に伝わりやすくなります。
また、エピソードに登場する人物の言葉を会話調で話す際にも、変に言い回しを意識するよりも、その人物がその言葉を発した際の状況や気持ちを想像し、その人物になりきって語ることで、自ずとその言葉に適した言い方になっていくものです。
ということで、まず、思いを込めるということを意識されるとよいでしょう。
ジェスチャーを用いる
2つ目は「ジェスチャーを用いる」ということです。エピソードを語る際に、ジェスチャーはかなり有効です。
一般にジェスチャーには次のような効果があります。
1 聞き手の関心を引く…視覚的な刺激によって、聞き手の関心を引き注目させます。
2 伝えたい内容を強調する…ジェスチャーによって、話している部分を強調することができます。
3 わかりやすくする…ジェスチャーで内容を説明したり、区切りを表したりすることができます。
4 感情を伝える…自分の感情をジェスチャーに乗せることで、聞き手に伝わりやすくなります。
このように、ジェスチャーによって話の内容をより効果的に伝えることができます。ぜひ、ジェスチャーも交えてエピソードを語りたいものです。
ところで、ジェスチャーを行う際に、気をつけるとよいことが3つあります。
1 片手だけを動かすのは控える(規則性が感じられず、感情的というイメージを聞き手に与え、信頼性が高まらないそうです)
2 左右対称の動きをする(意図的で規則的な動きに、聞き手は信頼感を覚えるそうです)
3 大きく動かし過ぎない(大げさに見えてしまうので、胸の前に1辺が肩幅程度の正方形を想定し、その中で動かすとよい感じになるそうです)
(参考文献:矢野香(2022)『最強リーダーの「話す力」』ディスカヴァー・トゥエンティワン)
ものを準備する
3つ目は「ものを準備する」ということです。
実は、エピソードを語っても、なかなか生徒に理解されないことがあります。
理由は、生徒によってはエピソードの中に出てくる言葉の意味がわからなかったり、その人物について知らなかったり、ものや場所について知らなかったりするためです。
これではせっかくのエピソードの内容も、校長先生の思いも伝わりません。
このようなことを少なくするために、必要に応じて説明用の小物を準備するとよいでしょう。具体的には、次のようなものです。
・写真
・実物
・文字カード
・映像
このような小物を使って補足説明をすることで、より具体的に、より視覚的に、生徒にエピソードを伝えることができます。
具体例は生徒の身近なものにする
わかりにくい言葉や状況を説明するには、小物を使う他にも、具体例をあげる方法があります。
例えば、「初心に帰る」という言葉の説明をする場合、ピアノの練習などを例にあげて「習い始めたころの素直な気持ちになってもう一度取り組んでみることだ」と説明したりします。
この具体例にも、効果的なものとそうではないものがあります。
効果的なのは、生徒にとって身近に感じられるものです。身近なものの方が、生徒にもわかりやすく関心も高いからです。
例えば、生徒全員が共通理解している学校行事とか、生徒のほとんどがイメージすることができる部活動や授業、定期テストなど、学校生活に関するものがよいでしょう。ただし、個人が特定できるものを例にあげる場合は慎重に行います。
その他に、校長先生自身の中学生時代の体験を例にするのも、生徒の関心が高まるので効果的です。
3 校長先生の授業として語る
校長先生が学級で生徒に授業をすることは、通常は行われません。ということは、校長先生の思いを生徒に伝える場は、校長講話を除くと、ほとんどないということになります。
そういう意味では、校長講話は貴重な授業の機会とも言えます。そこで、講話を校長先生の特別授業と位置づけて、授業形式で行うことも、生徒の心を耕すために有効なのではないでしょうか。
本書で紹介しているエピソードの中には、人生の岐路に立たされた人、困難を前に悩んだ人、努力を続けた人、発想を変えて乗り切った人など、いろいろな人々が登場します。
それらの人々の心情を思いやったり、迷いに共感したり、どちらを選択するかを考えさせたりすることは、道徳教育の一環としても意義のあることではないかと思います。生徒自身にとっても、自己の生き方を考えたり、人間としての在り方に思いを馳せたりするよい機会になるでしょう。
校長講話の時間はどんなに長くても10分程度だと思いますが、段取りよく進めれば、数名の生徒に発言をしてもらうことも可能です。
授業形式で行うことで、生徒自身も考えることになり、より生徒の心に残る講話となります。
4 生徒の感想を募集する
講話についての感想を募集することで、生徒はもう一度講話と向き合うことになり、校長先生の思いも伝わりやすくなるでしょう。
対応が大変ですから、希望する生徒だけに書いてもらうことにします。感想は、本人の許可があれば校内放送などで紹介します(名前を伏せてもよいでしょう)。
他の生徒も、感想を聞くことでもう一度講話と向き合うことになり、効果的です。
生徒にとって、校長先生はいつでも特別な存在です。
特別な存在である校長先生の講話ですから、長く生徒の心に残り、生活の指針となっていくものと思います。
印象的な講話で、ぜひ生徒の心を整えていってください。
-
 明治図書
明治図書














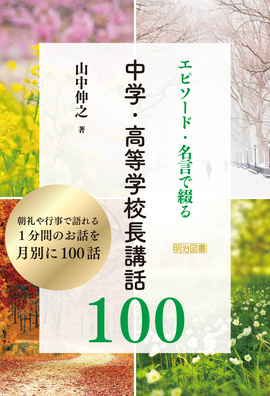
 PDF
PDF

