- イントロダクション
- 短く、印象的な講話で、聞き手の心を整えよう
- 4 April
- あいさつ[始業式] 新年度のスタートに向けて
- 気持ちの共有[始業式] 同じ小学生、同じ気持ち
- 実行の大切さ[始業式] 思いを行動に
- 学校生活の基本[入学式] 魔法の言葉
- 学びの意味[入学式] 「分かりません」が言える子に
- 学びの姿勢[入学式] 間違いは恥ずかしくない
- 明朗快活[朝礼] 笑顔の威力
- 友達[朝礼] 新しい仲間の誕生
- 自信を持つ[朝礼] 自信を持ってスタート
- 心構え[朝礼] 校歌に込められたもの
- 基本的生活習慣[朝礼] 早寝・早起き・朝ごはん
- 5 May
- 元気[朝礼] ゴールデンウィーク明けの魔法
- 心の持ち方[朝礼] 幸せの種
- 凡事徹底[朝礼] やるべきことをやる
- 自主性[朝礼] 自分で探し、自分で創る
- 自然に目を向ける[朝礼] 初夏の美しさ
- 6 June
- 命の大切さ[朝礼] 命はリセットできない
- 感謝[朝礼] 「当たり前」と思うな
- ポジティブ思考[朝礼] 雲の上はいつも晴れ
- 切り替えの大切さ[朝礼] 周りを変える? 自分が変わる?
- 動じない心で[朝礼] 気持ちを整える
- 自制心[朝礼] 天に唾すること莫れ
- 7 July
- 安全遵守[朝礼] 自分の身は自分で守れ
- 学習に取り組む姿勢[朝礼] 勉強は何のため?
- 克己[朝礼] 掃除は何のため?
- 幸せの条件とは[朝礼] 何が幸せを決めるのか
- 自由とは[終業式] 夏休みのあなたは?
- 夏休みの安全[終業式] 元気に再会しよう
- 夏休みの過ごし方[終業式] 「本物」に触れる夏に
- 8 August
- 再会の喜び[始業式] 元気に登校ありがとう
- 自己を見つめる[始業式] ヒーローの二学期
- 時間の大切さ[始業式] 一日一日を大切に
- 心の強さについて[朝礼] 心頭滅却すれば
- 勇気[朝礼] 伝える勇気が命を守る
- 自然環境について[朝礼] 温暖化について
- 礼儀作法について[朝礼] 礼儀と作法は何のため?
- 9 September
- 誠実[朝礼] 正直になる勇気
- 自己有用感[朝礼] あなたは大切な存在
- 夢や希望[朝礼] 百年後の世界は
- 偏見の防止[朝礼] 思い込みに気を付けよう
- 元気溌剌[朝礼] 自己暗示をかけよう
- 10 October
- 自然を愛する心[朝礼] 「かおり」を感じる力
- 自己判断[朝礼] 自分で確かめ、自分で考え、判断する
- 目標を決めて[朝礼] 「○○の秋」を実現しよう
- 畏敬の念[朝礼] 大きな力を敬う気持ちを
- 約束を守る[朝礼] 約束を守るのは誰のため?
- 体力づくり[朝礼] 東京オリンピックを知ってる?
- 11 November
- 努力の大切さ[朝礼] 気づかないけど確実に
- 大きな視野で[朝礼] 悩んだときは空を見上げよう
- 自然の豊かさを感じる[朝礼] 美しい秋を感じよう
- 備えの大切さ[朝礼] 厳冬に備える
- 叱られる意味[朝礼] 大切だから叱る
- 言行一致[朝礼] 「大きな言葉」と「小さな行い」
- 12 December
- 感謝で一年を終える[朝礼] 母の恩に報いる
- 安全第一[朝礼] 世の中が忙しい時期に
- 自律の心[朝礼] いつも心に妖怪を
- 真実と事実[朝礼] 自分を振り返ろう
- 謙虚さ[終業式] 心で手を合わせる
- 感謝を伝える[終業式] お陰様の精神で
- 家族の時間[終業式] 一番大切なもの
- 1 January
- 平時のありがたさ[始業式] それは、本当に当たり前なの?
- 夢と希望[始業式] 「増す増す」の新年
- 志を持とう[始業式] Be Ambitious
- 努力[朝礼] 自分と向き合おう
- 親切の大切さ[朝礼] 情けは人のためならず
- 友達と共に[朝礼] 睦月って、どういう意味?
- お金の価値を考える[朝礼] お金の貸し借りは、なぜダメなの?
- 2 February
- 心と体を鍛える[朝礼] 鉄は熱いうちに打て
- 心を見つめる[朝礼] 鬼は外・福は内
- 時間を大切に[朝礼] 2月は逃げる
- クラスづくり[朝礼] 雪の結晶の如く
- 反省と改善[朝礼] 調整の大切さ
- 自己を見つめる[朝礼] 津田梅子の生き方から学ぶ
- 3 March
- 自律の大切さ[朝礼] 自分を動かすのは?
- 叱られる意味[朝礼] 叱られる幸せ
- 夢と希望[朝礼] 春夏秋冬の神様
- 成長の春[朝礼] 積み重ねの大切さ
- 出会いの尊さ[修了式] 一期一会
- 笑って終わろう[修了式] 終わりよければすべてよし
- 気持ちの整理[修了式] 区切り・けじめ
- 職員研修
- 学級開き前に 新たな出会いを希望ある出会いに
- 教育論と教師考 信念を持って教育に当たろう
- 指導方針 心を鍛えて力を発揮させる
- 授業について 授業の基礎基本を習得しよう
- 自主 自ら考え行動させる
- 信頼 子どもの力を信じて
- 学ぶ姿勢 目標の教師を見つけよう
- 返事の指導 返事ができる子を育てよう
- 効果的な指導 「当たり前」を疑ってみよう
- 自律 「内なる声」を育てよう
- リーダー論 学級集団のリーダーに必要な資質
- ルール徹底 千丈の堤も蟻の一穴から
- 友達関係づくり 強固な友達関係づくりを
- 授業のねらい 授業における人格形成
- 授業規律 優れた授業の基礎とは
- 克己 「嫌い」で楽しさを学ばせる
- 教育観 時代が変わっても必要なこと
- 本質を見抜く 「原点」に返って考えよう
- 親心 将来を見据えた教育を
- 学級崩壊 チームの結束が崩壊を予防する
イントロダクション
短く、印象的な講話で、聞き手の心を整えよう
1 校長講話の意義とは?
昔から現在に至るまで、日本全国の小学校で学校長による講話が児童や保護者、職員、そして地域等の校外の諸団体に対して、集会や会議、行事や儀式の中で行われてきました。校長は、学校の代表者として様々な場で話す機会があり、校長は講話やあいさつをするのが当然と認識されています。
小学生時代の思い出として、「校長先生の話は長くてつまらなかった」などと、校長講話が引き合いに出されることがよくあります。小学校・中学校時代の校長講話の時間が、子どもにその内容が理解されていないだけでなく、「長くてつまらない我慢の時間」という笑い話として語られるものになっていることは、私たち校長にとって痛恨の極みとしかいえません。校長講話が子どもにとって、「単なる慣例的な儀式」として受け取られ、「つまらない我慢の時間」という思い出にならないためにも、自分の思いや願いが伝わるように、相手をひきつける話ができるように心がける必要があります。
近年、校長が職員に直接話をする機会が少なくなっていますが、職員に対する校長講話は、学校経営において非常に重要なものです。特に、現在は働き方改革や教育DX化等、教育現場は変化の真っただ中にあります。このような時代にこそ、スクールリーダーとしての校長の役割が重要になります。様々な課題がやってきたとき、職員が一致団結して取り組むことが大切です。職員をまとめ協力体制をつくるためには、子どもや学校、教育に対する考え方をすべての職員が共有することが重要です。朝礼や終礼、会議や研修で設定されている講話の場を決して無駄にせず、教師・教育者としての校長の考え方を職員に対して伝えるように努めるべきでしょう。
入学式や卒業式、運動会や音楽会などの行事の場は、保護者や地域の方に校長の話を聞いてもらうことのできる貴重な場でもあります。教科書にあるような一般的で儀礼的な差し障りのない話を述べる場にするのではなく、「校長の話は面白い。納得できる」と思われるような話ができるようにしたいものです。保護者や地域の方に、興味を持って聞いてもらえる話ができ、指導観や教育観を伝えることができれば、学校の経営方針や子どもへの指導方針を理解してもらうことにつながります。
以上、校長講話は、自身がこれまで培ってきた人生観や教育観を基盤に、学校の代表者としての思いや考えを伝えるための重要な場です。
それぞれの対象者に応じた話を心がけて、聞く人の心に残り、聞く人が楽しみに待ってくれる講話をして、教師・学校の代表者としてメッセージを伝えることで、学校教育活動に関わるすべての関係者に、安心して学校運営を任せてもらえるようにすることが、校長講話の意義だと私は考えています。
「生き方」を伝える
子どもに対する講話の意義は究極、「生き方」を伝えることにあると思います。自分の体験を通じて感じたことやその時々の社会的な話題や流行、時事ネタやニュース、昔からの言い伝えや偉人の言葉等を通して、人として大切にしなくてはならない考え方や生き方などを、子どもに訴えかけたり考えさせたりすることも、教師の大切な役割でしょう。
物事を前向きに考え公平公正に捉える姿勢の大切さを伝えたり、自分や他人と誠実に向き合って生活する大切さを訴えたり、努力や勤勉について考えさせたりと、人として恥ずかしくない生き方について、全校の子どもに一斉に伝えることができるのは、校長の特権でもあります。
毎日直接子どもを指導する担任や授業担当者とは異なり、校長は全校の子どもに対して大きく広い見地から伝えることができます。子どもにとって「校長先生」はステータスであるため、影響力は小さくはありません。日頃から個々の子どもと密な関係を築くことは難しい反面、「少し離れた大きな存在」として、子どもの心に残る話を伝えることができると考えて語ることが大切です。
「学校(校長)理解」のために
保護者にとって、校長というのは、直接関わることはほとんどなく、日頃はそれほど意識しない存在ともいえるでしょう。しかし、我が子が学ぶ学校が、どのような教育方針で子どもを育てているのか、保護者にとっては高い関心事です。その意味で、「校長の考え方」イコール「学校の教育方針」となります。特に最近では、保護者の学校に対する理解がなくては、思いきった学校運営は難しくなっています。保護者の理解と協力を得ることが、校長の教育観を学校経営へ反映することを可能にすると考えましょう。学校経営方針を保護者に理解してもらうためには、校長の考えを理解してもらうことが必要不可欠です。
一年間のうち、校長が直接保護者や地域の方に対して話をする機会は、多くはありません。入学式や卒業式では、限られた保護者や地域の方(1年生と6年生の保護者)にしか話を聞いてもらえません。コロナ禍後は、学校行事の精選が進み、保護者や地域の方に直接語りかける機会は、さらに少なくなっています。だからこそ、保護者や地域の方に語る機会を貴重なものと考えて、自分の教育観や経営方針を理解してもらうことができるように、話材を精選し相手の心に伝わるような話し方を心がける必要があります。子どもの印象に残る話を心がけることで、結果として子どもから保護者に校長の考え方や人柄を伝えることにもつながります。
直接言葉で伝えられなくても、学校だよりやホームページを活用して、多くの地域の方に、校長の考えを伝えることもできるでしょう。授業参観や学級懇談会で、様々な教室に分かれて参加している保護者に対して、オンラインを活用するなどの工夫によって、保護者に語る機会をつくり出すこともできるでしょう。
教育観・指導観の伝達と共有
語る機会が最も多い相手が、勤務する学校の職員です。朝礼や終礼、会議や研修が開かれる度に、必ず校長から話をする機会が与えられています。これらの場を、形式的なあいさつや教育委員会からの指示伝達だけで終えるのは、非常にもったいないことです。朝礼や終礼、会議や研修の場では、指示や伝達についての確認の他に、子どもの実態やトラブル把握、行事や授業の取り組みについて具体的な話し合いも行われます。このような場でこそ、授業や生徒指導における教師の姿勢について職員とともに考えたり、自身の指導観や教育観を伝えたりすることが重要です。校長の話や考え方をすべての職員に理解してもらえるとは思いません。しかし、たとえ自分と考え方が異なっていたとしても、校長としてのメッセージを伝えることで、子どもや教育に対する気持ちは、同じ教師として通じるものではないでしょうか。どんなときでも「特に伝えることはありません」などと言う校長に信頼を寄せる教師はいないでしょう。相手が職員だからこそ、一人の教師として指導観や教育観を伝えることに努めることが、結果として職員をまとめ、同じ方向へ進む職員団をつくることにつながると思います。
2 校長講話に必要な要素
学校に関わるすべての関係者に対して、興味を持たせ心に残るような校長講話にするためには、話材選びや話し方を工夫するなど、様々な要素が必要になります。
心に響く話材選びのコツ
講話の題材になる素材は、日常の至るところで見つけることができます。朝目覚めて窓から見える景色がどのように映るのか、新聞やテレビから得た情報から何を感じたか、自分の気持ちがどのように変化したか……。たとえ、道端に生えている雑草でさえも、聞く人の心に響く講話の材料になると私は考えています。例えば、
《道端に生えている雑草を見ました。誰の注目をあびることもありません。水や肥料をもらうこともない。邪魔者にされて踏みつけられることもあるでしょう。でも、だからこそ命の力強さを感じるのです。だからこそ、生きる尊さを教えられるのです。……》
というように、話をつくることができます。要は、身の回りにある物や起こる出来事をすべて教育に関わるものとして捉えるという意識で生活する姿勢が、講話の題材を引き出すことになるのだと思います。そして、子どもや保護者、職員に何を伝えたいのか、伝えなければならないかを考えながら日常を過ごす習慣を身に付けることが大切です。今の時代、言い方は間違っているかもしれませんが「教育バカ」になることが、校長講話の題材を見つけるために必要だと思います。
相手に伝わる話をするために
本音で語る言葉には力があります。たとえつたない表現であっても、聞く人の心を動かします。発した言葉が「自身の言葉」でなければ、聞く人の心に届く話にはなりません。「この人は、心の底から本音でそう考えているのだな」と、相手に受け取られることが必要です。そのためには、どれだけ強い気持ちがあるかが重要です。出来合いの原稿を借りて、「とりあえずその場しのぎで話せばよい」という気持ちでは、相手の心に響き記憶に残る講話をすることは不可能です。自分が心から感動し子どもや職員、保護者に伝えたいと思うことを、自分の言葉で語ることが重要です。
表現技術を磨く
原稿に目を通しながら読めば、間違いなく話の内容を伝えることはできるでしょう。しかし、それでは相手の心に突き刺さる講話にはなりません。時にはおだやかな口調で話しかけ、またある時は力強く訴えかける。大きな間をとって黙って見回すこともできるでしょう。体を動かしたり大きくジェスチャーを交えたりしながら話すこともできるでしょう。このように大勢の人を前にして話をするときに有効な技術を活用することも、聞く人をひきつけるためには重要です。
伝えたいという強い思いで、いかに相手に伝わるように話すことができるかが、講話の成否を分けます。実際に講演会に足を運んで学んだり、テレビやインターネットなどで上手な人の話し方を学んだりして、講話のための表現技術を磨くように努めることが大切です。表現技術を高めるために意識を持って経験を重ねることで、聞く人をひきつける講話ができるようになっていくはずです。
-
 明治図書
明治図書- 掲載のテーマ、その内容と、今子どもたちに保護者に教職員に伝えたいことをリンクさせて参考にできた。2025/9/6moco
- 行事や全校集会、職員用にお話できる内容が月毎に掲載されており、タイムリーに活用できます。今後も学校の実態に合わせて参考にさせていただきます。2025/5/550代・小学校管理職














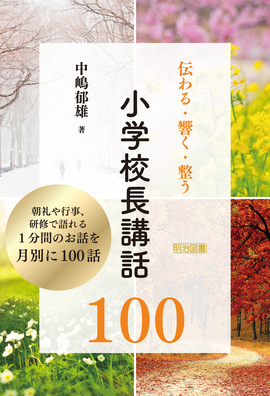
 PDF
PDF

