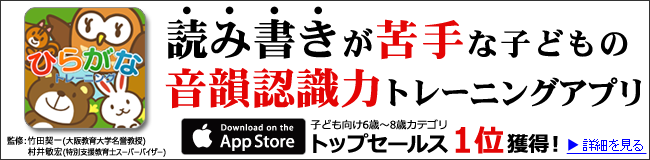- 特集 LD,ADHD対応の“黄金の三日間”
- LD,ADHDの子どもとの出会いと対応策
- 入学式からトラブルが発生した子
- /
- 入学式からトラブルが発生した子
- /
- 遅れや負けに感情が抑制できなくなる子
- /
- 遅れや負けに感情が抑制できなくなる子
- /
- 興味のあるものに出会うと感情が抑制できなくなる子
- /
- 教師の話を最後まで聞かずにすぐに口をはさむ子
- /
- LD,ADHD対応の学級づくり
- 当番活動は一人一役で
- /
- 常に学級全体の子たちに目をそそぐ
- /
- 特性を踏まえたポイントはここだ!
- /
- 生活のルールを教える
- /
- ひとりぼっちにさせない担任の関わり
- /
- やってほしいことをほめて増やす
- /
- やってほしいことをほめて増やす
- /
- アスペルガー対応の“黄金の三日間”
- こんな時,感情の抑制ができなくなる!
- /
- こんな時,感情の抑制ができなくなる!
- /
- 学習不振の子どもとの出会いと対応策
- 初日からパニックになった事例
- /
- 三日目にパニックになった事例
- /
- パニックに視線を向けながら無視する
- /
- 担任にどんなアドバルーンをあげるか
- /
- 担任にどんなアドバルーンをあげるか
- /
- いかにしてアドバルーンをたたくか
- /
- こんな時,感情の抑制ができなくなる!
- /
- 真面目な子どもをまず大切にする
- 一人の子に学級全体が振りまわされた以前の反省点
- /
- 一人の子に学級全体が振りまわされた以前の反省点
- /
- 学習不振児対応の学級づくり
- 個別対応の前に学級全体をきちんとさせる
- /
- 個別対応の前に学級全体をきちんとさせる
- /
- ボスのプライドを守りつつ個別の支援をする
- /
- ほめる場面をつくってほめる
- /
- ほめる場面をつくってほめる
- /
- 入学式の日からおしゃべりな子
- /
- 特性を踏まえたポイントはここだ!
- /
- ミニ特集 グレーゾーンの子も分かる百玉そろばん指導
- TOSS百玉そろばんは「数概念」「数のかたまり概念」獲得に最適の教具である
- /
- 5までの数は,数概念の基本だ〜子ども用百玉そろばんで指導を〜
- /
- 数を固まりとして指導する
- /
- 玉の動きを見続けられない子どもができるようになった子ども用百玉そろばんの威力
- /
- A君に適した繰り下がりのひき算の指導法は減減法だった
- /
- 聴覚情報の入力を意識的に組み込む
- /
- 百玉そろばんを子どもにはじかせる「目」と「手」と「口」と「耳」を使うことになる
- /
- リズム九九と百玉九九で楽しく覚える
- /
- グレーゾーンの子も一瞬にして集中する百玉そろばん
- /
- TOSS障害児 ホームページの紹介
- 絵本の部屋 中谷結花氏のサイトへ
- TOSS障害児教育のキーワード
- リタリン
- /
- 読者のページ
- 巻頭言
- 雪谷小学校杉の子学級から学んだこと 子どもの持ちよる身近な問題は「教育学」の宝庫だ
- /
- 教育の力をすべての子どもたちに
- プロならADHD/LD役がいる模擬授業に挑戦しよう(その2)
- /
- 障害児教育と向山型算数の原理・原則 (第5回)
- 教室に「大きな渦」をつくり,巻き込め
- /
- 障害児教育と向山型国語の原理・原則 (第5回)
- 教室の障害児にも「知的な国語の授業」を可能にする向山型国語
- /
- 障害児教育と漢字指導の原理・原則 (第5回)
- 従来の漢字カードでは,なぜできないのかを分析する
- /
- 大森校長からみた障害児教育 (第3回)
- 保護者に受診を勧める手続き
- /
- 竹川教頭からみた障害児教育 (第3回)
- 保護者との信頼関係を築く(1)
- /
- ADHDの子とぶつかりあった日々 (第3回)
- S君にとっても担任にとっても安心できる居場所
- /
- K−ABCを向山型授業にいかす (第2回)
- 筆順を唱えて空書きする
- /
- 重度・重複障害児の指導 (第2回)
- 重度・重複障害児の理解のためには,教師修業が必要である
- /
- 医療との連携のポイント (第2回)
- 子ども以上に親への支援を大事にする
- /
- アスペルガー症候群の子への指導 (第2回)
- 医療への連携 担任が伝えなければならない場合
- /
- TOSS障害児教育情報コーナー
- ADHDの疑いがある子どもの保護者と懇談をする際の手順〜新しく始まった二つのML〜
- /
- 編集後記
- /
- 第5回TOSS特別支援教育・研修の集い案内
- /
- グラビア
- 第4回TOSS特別支援教育ML・研修の集いin大阪
- /
編集後記
▲「教科書の28ページを出して3番をやりなさい」という指示が入らない子がいることは今や本誌の読者には常識になりました。ワーキングメモリーが少ないから複数の指示が分からない。しかし,「一時に一事の指示」を出せば分かってできるわけです。このような配慮は実は一生必要です。
例えば,そのような子が大きくなってレストランで働き始めたとします。上司から「お皿を洗って,その後ニンジンも洗って,ニンジンを洗い終わったらジャガイモの皮を剥いておいて」などと立て続けに言いつけられたら言われたとおりに働けるでしょうか。働けません。就労においても「一時に一事の指示」を上司に出してもらう必要があります。「教室の障害児」に行われている配慮は将来の就労場面にも引き継がれる必要があるのです。(梅永雄二『LD(学習障害)の人の就労ハンドブック』エンパワメント研究所 参照)
▲第4号の特集「LD,ADHDの子のトラブルこの場面でこの指導」に次のような感想をいただきました。
「久しぶりに一気読みの『教室の障害児』。特集がすごくいい。この雑誌が教室で一人の子の扱いに悩んでいる普通の先生にこそ読んでほしいと思っていることが分かります。見開き2ページに日々格闘している先生のさまざまな対応の仕方が分かります。きっと私のクラスの子と似ていると思って読むことと思います。たいへんなのは私だけじゃない,日本中でこんなに悩んで戦っている先生がいるんだという連帯感はどんなにか勇気が出るでしょう。職員室でまわして購入の希望を取ってあげたいとTOSSの雑誌で初めてそう思いました。第1号とあわせたら鬼に金棒です。」
▲日々の教室で障害をもつ子にどう対応したらいいのかがすぐに分かる,明日の授業に役立つ,これが本誌の主張であり,他の障害児関係の雑誌との大きな違いです。本号の特集「LD,ADHD対応の“黄金の三日間”」でいえば,甲本先生のプリントぐちゃぐちゃ事件,水野先生の体育館に入ってこない子どもの話が本誌の特長を明確に示しています。この二つの原稿は一つの場面だけを取り上げて詳しく再現し対応法まで書かれています。だから分かりやすいのです。小林先生のパフェ事件も目に見えるような印象的な場面です。
▲ミニ特集「百玉そろばん指導」では5までの合成・分解がキーワードとして出てきました。求む解説原稿。
▲校正でお願いがあります。「」の中の「」は『』に変えます。例えば,「『ごめんね』と彼は言った」など。
▲横山先生が前号に続いて力を入れて書かれている「ADHD役がいる模擬授業」をついに第6号で大々的にとりあげます。椿原先生の「ある」と「いる」の授業も特集されます。ご期待ください。
(大場 龍男)
-
 明治図書
明治図書
















 PDF
PDF